
誤学習できるということは
正の学習もできるということを意味します。
学習はできる
その方向がプラスの方向か、マイナスの方向かの違いで
その違いは、食形態・食具・介助方法含めた食環境の適否にあります。
食事介助を拒否する方
食事中の大声が止まらない方
口を開けてくれない方
ためこんで飲み込んでくれない方
たくさんの方が食べられるようになりました。
私は食べ方の観察ができるようになりました。
食べ方に反映されている困難も能力も特性も洞察することができるようになりました。
だから、重度の認知症のある方でも正の再学習を援助することが叶います。
逆に言えば
「〇〇という状態の人にどうしたらよいでしょうか?」
というカタチの質問には答えられません。
〇〇という状態を直接見てみないとわかりません。
食事介助を拒否するといっても、拒否する必然は人によってまったく違うからです。
食事中の大声が止まらないといっても、大声が出てしまう必然はまったく違うからです。
Aさんは、オーラルジスキネジアがあることを介助者側がまったく気がついておらず
適切な介助ができていなかったからであり
Bさんは、ポジショニングの不適合によって顎がズレてしまっていたからでした。
かきこみ食べをするからと、小さなスプーンを提供されても結局、かきこみ食べをしています。
Cさんは、上肢操作能力を十分に発揮できずにいてその代償としてかきこみ食べをしていたし
(手の問題)
Dさんは、とりこみ方を誤学習していたために代償としてかきこみ食べをしていました。
(口の問題)
口を開けてくれないと言われていた方の中には
Eさんは、原始反射様の動きが出ていることを介助者側が気づかず、口の中に食塊を入れられ続けてきたので口を開けるタイミングを図ることができなくなっていたし
Fさんは、パウチ状の栄養補助食品を押されることで水分と栄養を摂取していたので開口すると舌がパウチの口の形状に合わせてUの字型になってしまっていましたし
Gさんは、口輪筋が硬くなっていたので自身では食べる意思はあっても、おちょぼ口のようになってしまい開口できませんでした。
ためこんで飲み込んでくれないと言われた方は
Hさんは、口腔期が長い方で食塊が口の中に残っているから口を開けないだけでしたし
Iさんは、誤介助誤学習のために舌が板のように硬くなり送り込みができなくなっていましたし
Jさんは、オーラルジスキネジアのために送り込みに時間がかかっていました。
Aさん〜Jさん皆さん20分程度で完食できるようになりました。
皆さん状態像はまったく違いますし
私の対応も人それぞれ、変化に応じた対応をしていきました。
「大声 → 声を出さなくなる対応」
「かきこみ食べ → 小さなスプーン」
「口を開けてくれない → 開けてもらえる声かけ」
「溜め込んで口を開けてくれない → 口を開けてもらうスプーン操作」
などの「〇〇という時には△△すれば良い」というようなハウツーは、あるわけがないのです。
かつて、養老孟司が人に対して「あぁすればこうなる」なんてものはない
と喝破しましたが、なぜか、認知症のある方に対してみんなが求めているのが「ああすればこうなる」です。
そして、あまたある本や研修で伝えられているのも「〇〇という時には△△する」です。
だから、結果が出せないし
仮に、結果が出せたように見えても、いつの間にか別の問題が出てくるのです。
そのようなケースを繰り返し繰り返し見聞きしているはずなのに、
自身の思考回路や対応に疑問を持てずにいるのです。
HDS-Rが0/30点だったり
検査すらできなかったり
その場の会話が成り立たなかったり
介護拒否や介護抵抗の強い方や
大声や暴言暴力のある方などの重度の認知症のある方でも能力を発揮しながら暮らしています。
ただ、その能力発揮が不合理なだけなので合理的に発揮できるように援助すれば良いだけです。
だから、食べることの困難を協働して克服し、もう一度食べられるようになるのです。
認知症のある方や生活期にある方の場合に
食べる困難の多くは、実際には不適切な食事介助に適応した結果つまり誤介助誤学習が原因です。
誤学習ができるということは、正の学習もできるのです。
たくさんの方がもう一度食べられるようになる過程を協働してきましたが
そのたびに思うことは、
どんなに重度の認知症のある方でも能力を発揮しながら暮らしているということです。



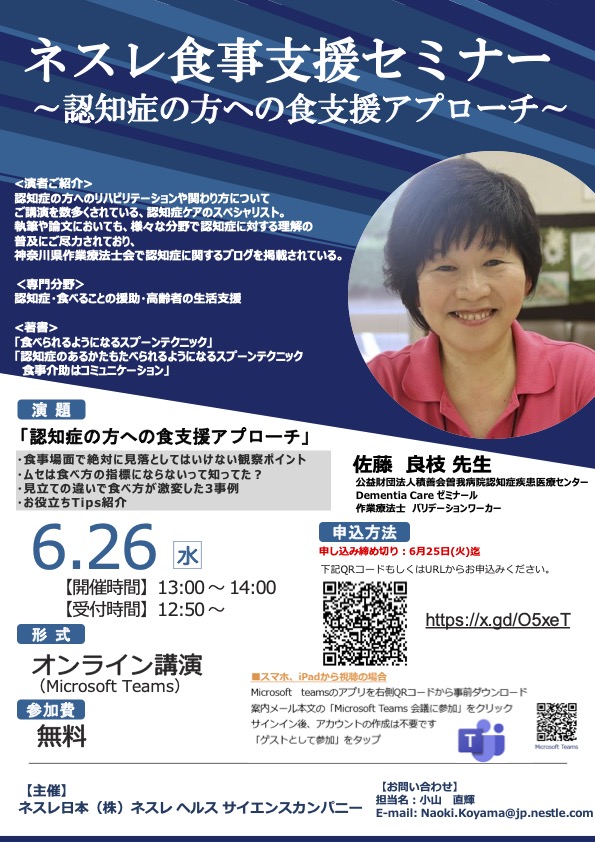







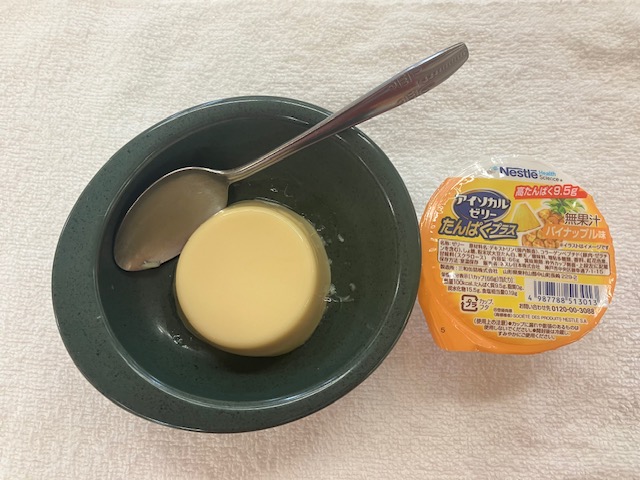

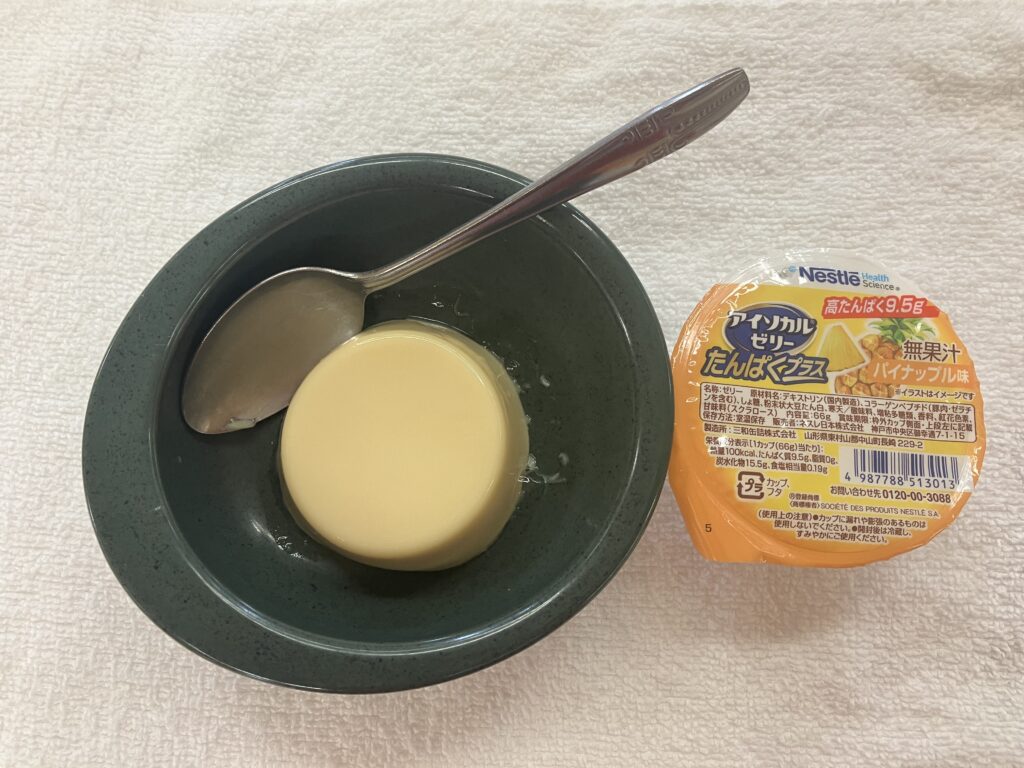

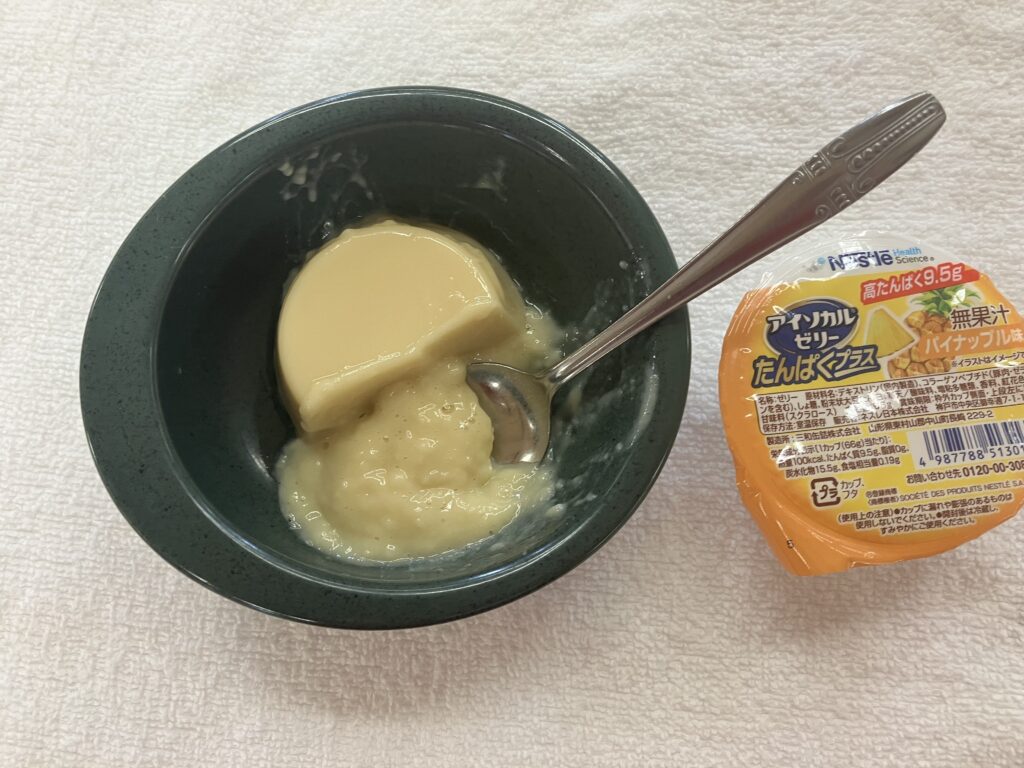

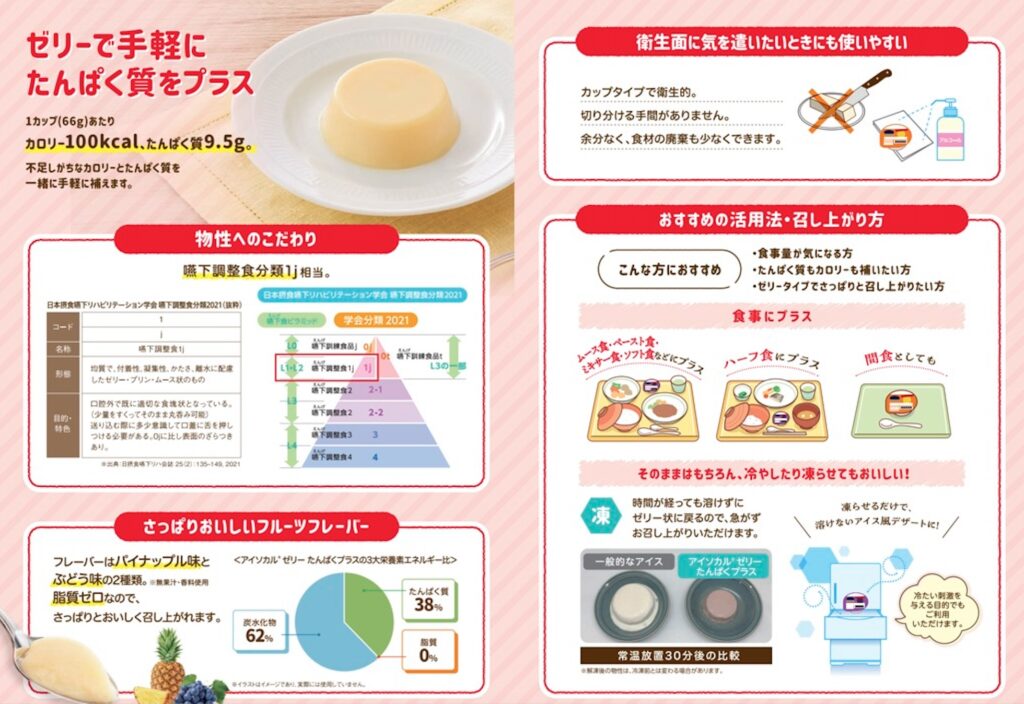


最近のコメント