廃人症候群とはずいぶんな言葉ですけど、そうした実体も少なからずあるのだと思います。私はこの言葉は知らなかったのですが、皆様はご存知でしたか?
いろいろ難しい問題がありますが、とりあえず皆が問題を隠蔽せずに取り組み、検討し解決の努力をすることは必要だと思います。
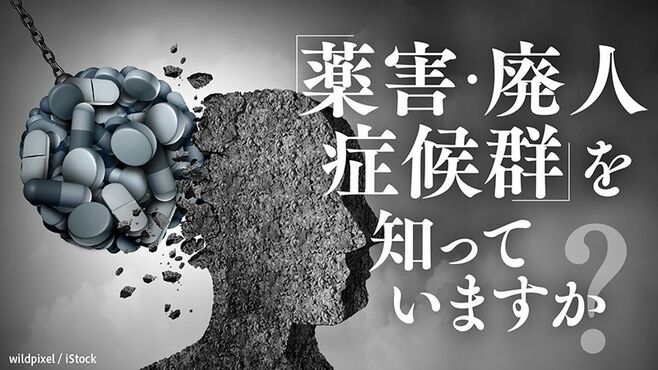
「薬害・廃人症候群」を知っていますか? 東洋経済ONLINE
連載が止まっているのが残念です。言葉の問題かな?
他にも精神医療問題はいろいろありここへ来ていろいろと表面化しつつありつます。(また後で加筆しますが)
私は小学生の時、初代ジャニーズの時から喜多川の性的虐待問題について知っていました。性的なことは全く知らず、もちろん具体的なことは知りませんが、週刊誌の見出しを見ただけでも何となくわかってしまいショックを受けたのです。
子供はそういった超能力者的なところがあるのは、私のように幼児期の記憶が鮮明な人や、子供を育てたことがある人はわかると思います。
大人は汚い、芸能界は汚いと思い、それ以降はグループサウンズやフォークソングのファンでしたが他の芸能には関心がなくなりました。人間不信にも繋がりましたが、反体制反権威主義にもなりました。
誰もが少なくとも噂レベルでは知っていたのに隠蔽され、60年も続き1,000人以上もの被害者を出したのか?
大きな理由の一つは精神科医なども含めて殆どの国民の性的虐待PTSDの理解があまりにも乏しかったからです。昔はもちろん今でもそうだと思います。もちろん他の虐待PTSDについても。
精神疾患の殆どは心理的虐待を含む虐待PTSDです。
性的虐待トラウマの影響は何十年も経ってから休火山のように噴火して、激しい症状を出現させることが多いです。もちろん自殺者も少なくないことは十分予測できます。他にはアルコールや薬物依存症になったり、症状は何でもアリです。
数年~数十年経つと危ないかもしれない、というより危ない人が殆どでしょう。
告発者の多くは性的虐待PTSDの激しい症状と戦いつつ薬を飲んだりしながら活動しています。その薬の副作用や離脱症状、後遺症もあるのでたいへんです。
既に向精神薬害など二次的な被害にあっている人もいるし、おそらく暴力団などの被害にあっている人もいます。もちろん何度も自殺未遂した人も多く、働けなくなり生保をもらっている人もいます。
彼らのうち何人かは「自分は加害者です(でした)」とも明言しています。
私は喜多川のことを知って以降は、ジャニーズ系なんかバカにしきっており関心もありませんでしたが、すっかり彼らのファンになってしまいました。
活躍中のジャニタレはノーテンキに笑顔で歌って踊ってお芝居をしていますが、それが症状という見方ももちろん可能です。精神の解離という防衛機制があり解離性健忘などPTSDの解離症状もあるので。
彼らの足元は薄氷かもしれないし、時限爆弾の導火線はもはや短いのかもしれません。
今後、アルコールや薬物依存症になったり、自殺する人も多いことが予測できます。
解離性健忘のため嘘を言うわけではないにしても、実際にはあったことを「知らない、覚えていない」という人も少なからずいると思います。過去のタレントもほぼ全てそうでした。一旦は虐待を認めても「そんなことはなかった、憶えていない」と戻ってしまいます。
未だに喜多川を賞賛、尊敬しているのはグルーミングやマインドコントロールの影響が続いているとも言えますが、ストックホルム症候群でもあるかと思います。
加害者を恨めば良いわけではもちろんありませんが、被害を受けているのにむしろ加害者に感謝している人がDVや虐待など他者に攻撃性を向ける傾向にあります。
やはり「事実の子たれよ、理論の奴隷となるなかれ」です。
事実を尊重しそれに基づいて考えなければ解決もしません。
一般に虐待被害者が虐待することが多く虐待は連鎖することや、犯罪者もまた虐待された人であること知られていますが、もちろん虐待しない人もいます。
一説によると虐待された人が虐待するのは7割だとか?
前者と後者の違いについて荒っぽく言えば、前者は虐待された苦しみに向き合わず克服の努力はせず誤魔化すために行動化する、後者はPTSDの苦しみを受けうつ病(と敢えて言っておく)などで苦しんでも、それを自分のこととして引受け、向き合わざるを得ないので何とか対処、克服しようとする、ということです。たとえ成果が得られなくても…
こうした意味では告発者よりも活躍中のタレントの方が危ないのかもしれません。
ジャニー喜多川自身もまたそういう人です。
彼は朝鮮戦争に従軍または軍属として関わりましたが米兵にレイプされたとかそれ以前に父親にも性的虐待を受けていたという話もあります。その妥当性や真実性はともかくとして何かそれに近いことがなければあんなに大規模な性加害者になるわけはありません。他のトラウマもあったのでしょう。
その父親もまたどうか?などと思うわけですが、私はこのような問題を長年追求しているので具体的ではなくともある程度のことはわかっています。
私の家系も精神病の家系であり語弊はありますが「呪われた家系」でもありましたが、700年も先祖を辿って大いに腑に落ちたことがありました。一応由緒ある家系でもあります。
ジャニーズはハッキリ言ってエンタメの進歩や質の向上も阻害してきたと思います。
もはやJPOPがKPOPに追いつくことは考えられません。
一つはここでは触れませんがリズムの基本が身についていないということ。これは楽曲提供者の山下達郎なども基本的には同じです。
やはり大事なことは彼は自分が受けた虐待の苦しみに向き合わず、それを誤魔化すために性加害を行い、それを行ってしまい「うまく行ってしまった」がために止めることもできず、老人になるまで続けたという事実です。金儲けはできてもこうした人間から価値のある芸術が生まれるわけはありません。
怒る人も多いと思いますが、ジャニオタと言われる人たちもまた、ストレスの原因となるような自分の問題や周囲の問題に向き合って解決しようとするのではなく、「輝く少年たちから夢と愛と勇気を与えられ」誤魔化しつつ頑張っているように思われます。それがあってはいけないとは言えませんが。
実際にテレビによく出たりCDが売れているからといって、ジャタレの人気はそれほどあったわけではなく、嫌いだとか関心がないという人が多いはずです。むしろ一部の人だけを対象にしていましたが、しコアなファンも少なからずいてかなりのお金も出すので事務所は儲かるしメディアやマスコミの支配も可能だったわけです。
もちろん私の友人知人にジャニーズが好きな人はいないし、何人かの女友達に聞いてみたら好きな人もいてその人は熱狂的だったけど殆どの人は好きじゃないし関心もない、ということでした。
言ってみれば人気も幻想だったわけです。多分に無自覚ですが事務所側はその幻想を上手く乗っかって支配するのが上手かった。そもそも性加害は皆さん知ってたのだからメディアやマスコミの方から拒否してテレビにも出さず、他のタレントを発掘して出せばその方が視聴率も上がったでしょう。
皆が共同幻想に支配されていたとも言えます。
幻想は条件が整えばあっさりと幻滅に変わりますが、そのためには隠蔽されていた事実を知るべきでしょう。
嘘をついて問題を隠蔽したり、見て見ぬふりをして無かったかのようにするからこそ悪質な幻想は大きく強固なものとなります。人を騙せば騙された人もまた人を騙します。
止めれば良いだけの話であっても、でも止められない、止められなかった。ウクライナを見ればわかるように戦争だって似たようなものです。もちろんイジメの問題なども。
基本的にはファシズムも同じだけど、多くの人を巻き込んでしまえばもう止められません。
新興宗教にも似た構図です。伝統宗教があるのに新興宗教は要らないと思う人も多いでしょうけど、伝統宗教は自分の内面と向き合い常々自分を顧みることでもあり敢えて自分に課題を課すことになりますが、新興宗教はまやかしであっても安易な救済や利益を与えます。
もちろん悪いばかりではないし新興宗教を全否定することもできませんが。
精神疾患も薬物で誤魔化すのは止むを得ない面もあるし、全否定するわけではないが害やリスクも高いし、やはり本質的な害のない治療を行ったほうが良いというのが私の立場です。
喜多川が死んでも、私が生きているウチにこの問題が表面化するとは思いませんでしたが、この機会に芸能界、メディア、マスコミだけでなく、日本の社会全体の浄化、適正化、正常化につながり社会全体が人権を尊重した精神的にも豊かなものになることを期待しています。
もちろん性犯罪や性的虐待だけでなく、他の犯罪や虐待を防ぐためにも必要なことです。
目先のことだけを考えるべきではありません。
ファシズムやスターリズムのようにこれから100年は問い続けていかなければならないと思います。
こうした問題に向き合い克服する努力を怠ったからこそ、毛沢東や北朝鮮の独裁の問題、ポルポトやチャウシェスク、プーチンとウクライナ戦争の問題も起こったと言っても良いと思います。
WW2が終わった時点で殆どのドイツ人はホロコーストを知らなかったそうですが、もちろん全然知らないわけではなく知ってて知らぬふりをしていたはずです。もちろん現場を見ていたわけではないし、そういう意味では知らなかったのですが。
大風呂敷を広げるのは私の悪い癖かもしれませが、そういう人は少ないし、いても良いだろうと思っています。
冷静に考えれば誰もそんなことしたくないし、全くする必要もないのに、絶対にすべての人がやらなければならないことになってしまう。しなければ殺される。
今後に役立てなければ喜多川の霊も(おそらく地獄から)浮かばれないと思います。
そうすれば彼の功績も反面はあったとこになるかもしれませんが、今のままでは彼の功績など認められません。基本的には有能なタレントやアーティストが出ることを阻害し、むしろエンタメの質の低下をもたらしたと思います。
暴力を使って(もちろん間接的に)告発者を攻撃したり殺害したり、政治家などの有力者に性的に上納をしたり、セクハラはもちろん枕営業をけしかた方ものった方もセクハラだし(お金よりもずっと悪質だし、売買春というより人身売買に近いか?)そういうことはもう止めるべきです。
「日本社会の闇」とか「心の闇」といった言葉で片付けているだけではいつまでも解決しない、そういうことは明るみに出して克服すべきであり、公序良俗に反することは違法ではなくても止めるべきであるということです。
そうしなければ進歩はありません。
とりあえずココでは、 J.ハーマン「心的外傷と回復」みすず書房 をお勧めしておきます。
増補度版は高いので、古本でそうではない白い表紙の旧版を入手したほうが良いと思います。数ページ付け加えられただけで、本文は同じです。
こちらはたいへん参考になります。私もほぼ同意見です。もっと早く世の中が変わって欲しいけど。
以下の動画の石丸志門さんの話はとてもわかりやすく参考になると思います。
精神科に10年以上通った体験を詳しく語っています。
それにしてもハッキリ言って精神科医はバカすぎ。
普通は初診で聞けばわかるし分からなければ治療が進まないことを10年以上もかかっている。
全体的にレベルは低いしたいていはこんなもんでしょうけど。
PTSDの場合特に薬は合いません。
その間、薬で余計に悪化するし、自殺未遂を繰り返すし、仕事もできなくなり生活保護になってしまうし。
他の被害者も向精神薬害の二次被害に遭っている人が多いです。
被害者1,000人以上とも言われており、今後もそういう人がどんどん増えるはずで、今は元気に輝いて歌ったり踊ったりしているタレントも数年数十年後には危ないです。
具合が悪くても頑張っている当事者の会の皆様には頭が下がります。
初代ジャニーズは好きだったんですけどね。ちゃんとハモってたしダンスも上手かった。


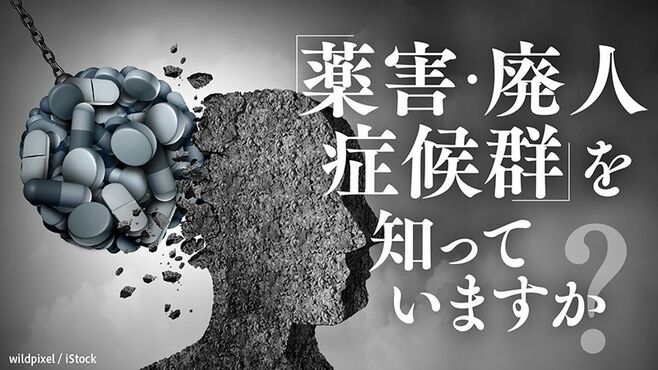











最近のコメント