【ROMとMMTの諸問題(ごむてつ)】
30年近く前のことだが、友人に「ロムって何のことだ?」って突然聞かれたので、「ROMっていうのはRead Only Memoryのことで、RAMはRandom Access Memoryで…」なんて頓珍漢な返答をしてしまったけど、聞かれたのはパソコンのことではなかった。
聞いてきたのは、当時同僚の友人OTである。
ROMもMMTも知らないOTなんかいるわけないだろ!と思うも知れないが、それがいたのである。
俺はもちろんROMもMMTも一応学生の時にはやったから一応知ってるけど。
ROMって何の略だっけ?関節可動域か? Range of Motionだっけ?
MMTは徒手筋力テストだっけ?Manual Muscle Test か?
正直、もう忘れた。思い出す気も調べる気もしない。
聞いてきた友人は、1980年代の初め米国の大学院に留学してOTの資格もとったのだが、米国ではROMもMMTもブルンストロームも聞いたことがないと言う。
米国の大学院に留学したOTは多いけど、彼のように米国でOT資格も取った人は珍しい。大抵の人は日本でOTの資格をとってから留学している。
(少なくとも当時は)米国のOT資格がそのまま日本で通用するわけではないので、日本に戻ってからまた国家試験を受けるのだが、専門用語は英語で覚えているし、米国では聞いたことがないような問題が出てくるし、たいへんだったらしい。
――――――――――――――――――――
今でもそうかもしれないが、私が一応OTだった2~30年前は短大や専門学校の2年生(大学だと3年か?)になると、RAMとMMTの実技テストは一大イベントであった。盆と正月とお祭りが一緒に来たように、教官も学生も急に色めき立って大わらわ。出来が悪いと落とされて何度も追試を受けなければならないことは、既に先輩たちから話も聞いている。あまり出来が悪いと単位がとれず留年になる。
その友人OTが「何であんなことやるんだ?」と言うので、「学生は人の身体に触れることも慣れてないし(今は慣れているのか?)、人に指示することも慣れてないし、そもそも実地テストなんかも受けたことがないだろうし、解剖学や神経・筋の知識のおさらいみたいなものだし、通過儀礼のようでもあるし…」なんて一応答えたのだけど、彼は全然納得してはいないようだった。
思い起こせば私も学生時代からあまり納得していなかったのだが。
正直言って、リハの学校に入ったときは、精神科志向は強かったものの特に決めていたわけでもなく、身体的なことや運動のことなどにも関心はあったのに、学校に入ってから徐々にOTには失望が強くなり、特に身障系には関心をなくしたのはROMやMMTがきっかけだった気がする。
もちろんそれ以外にも理由はいろいろあるけど。
――――――――――――――――――――
ROMやMMTが全く必要ないと言うわけではもちろんないので、念の為。
MMTは御存知の通り、中枢疾患だと殆ど意味をなさないし。
例えば筋ジストロフィーや頸髄損傷の不全麻痺とか、必要なら場合に応じてやれば良いと思う。
それにしてもやはり評価は臨床観察が主体であり、テストは一資料を得るだけで、そのための補助に過ぎないと思う。
テストの結果を積み上げても評価にはならないし、それだけでは治療目標やプログラムも立てられないだろう。今後いろいろなテストができてデータが得られるようになったとしても。
いずれにしても適用は限られ、必要に応じてやれば良いと思うけど、ROMもMMTも適切に行われているのだろうか?
OTPTの教義のように金科玉条になっていることは納得できないし問題かと思う。大げさに言えばOTの臨床的能力や技能のレベル向上をむしろ阻害している気もするし、そんなことばかりに労力や時間を使うのは無駄な気がする。
他にやらなくてはいけない重要なことがいくらでもあだろうし。
学生の勉強も臨床でも。
ROMテストや訓練の問題
俺はOTの学校に行く前は自転車の仕事をしていたので、その頃は直線が交わる角度なんてパッと見ただけで±0.5度単位なら正確にわかった。今は自信ないけど。
職人はそんなもんいちいち計っているようでは仕事にならない。もちろん確認のためには計るけど。
骨は直線ではないし計測ポイントもピンポイントではありえないので、そんなに正確にはわからないし、5度単位で良いならなら見ただけでわかるし、角度計を使えば精度が保証されるわけでもないし、そもそもデータが大事なわけでもない。
むしろ観察で状態像を把握しておくことは重要である。
きちんと観察・把握できていれば特にROMテストは必要ない場合も多いだろうし、関節可動域制限があるにしても、それ自体が問題なのかどうか?
セラピーの時だけROM訓練をやってもあまり効果はなく、直ぐに戻ってしまうのではないか?といった有効性の問題もある。
こういうのは有効だと思う。
スポンジでROM維持 ? 月刊よっしーワールド (kana-ot.jp)
前述の友人OTは訓練器具なんかも工夫して作っていたけど、そういうことをする人もあまりいないのでは?
なんで皆、あまり工夫しないんだろうか?という気もする。まさか今どきサンディングでも無いだろうし。
我々の頃は脳卒中の急性期には後のリハビリの妨げにならないようにROM訓練が必要だなどと言ってた気がする。適切に行えるかという問題もあるけど、むしろ看護や介護の役割という気もする。。
こんなこと書くとまた叱られそうだけど。
いずれにしても漫然とやるのではなく、必要な場合に適切に行うべきだろう。
――――――――――――――――――――
運動療法や機能訓練をきちんとやっていれば状態像の把握もできるし、要は動かせれるようになれば関節可動域も徐々に広がるし、当人自身でもある程度できるのではないか?
機能的なOTとか、神経筋促通手技とかファシリテーション・スキル、テクニックというのだろうか、ボバースとか?
やっぱり麻痺や上手く動かせないのを動かせるようにするのがリハの基本だろう。100%の回復は無理だろうし、限度はあるにしても。
そうしたことをきちんとやるならROM訓練を兼るだろうし、実際に動かせるようなって動かしていれば、ROMはある程度広がるはずだ。それでは支障があるならやはり必要に応じて適切にやれば良いだろう。
卒業生のOTいる病院に行くと何となく、あやしげな雰囲気を醸し出してROM訓練?をやっていたりした。
「痛みますかぁ~?」とかなんとか言ったりなんかしちゃって。
あれは一体何をやっているんだ?ストレッチか?
一対一でつきっきりでやると時間をとられるし、他にやることいくらでもあると思うのだが。実は何をやって良いのかわからなかったり、できないのでROM訓練をやってる人も多いのではないだろうか?
脳卒中のOTなど、ROMとActivityだけで良しとしている人はいないだろうか?
ROM訓練をやっているといかにもリハビリをやっているという自己満足がOTの側にも患者の側にもあるのかとも思うけど。温泉場のマッサージとかならそれでも良いだろうけど、医療としてやるのは問題もあるような…
悪く言えばリハビリごっこ、というのは言い過ぎか?
MMTは必要か?
ROMと違ってMMTは実際の臨床場面ではあまり行われておらず、もう忘れてしまったOTもいると思う。ご存知のように中枢疾患には適用できないし、適用の対象や範囲は非常に限られる。使わないものを学校でやってもしょうがないのでは?もっと基本と応用が可能となる考え方や方法を身につけることが必要かと思う。
たいして使いもしないのに、あたかも重要な臨床の基本のように扱うのも問題だが、むしろ一番大きな問題は、臨床の基本である運動学的理解の妨げになり、阻害していることではないか?と思う。もちろん知識それ自体が理解の妨げになるわけではなく、教育過程や理解や実践のプロセスとして。
筋の起始停止やら神経支配や主な動きを憶えてMMTを身につけると、運動の基本がわかったような気になってしまうかも知れないが、それだけでは全く応用が効かない。
もちろん、それらを知らなくても良いわけではないが。
MMTを身につけても神経・筋に関する学習にはなっても、運動の理解にはなかなか至らないのではないか?
実際に運動学的理解がMMTレベルに留まっている人も少なくない?というのは言い過ぎかも知れないが、OTもPTも臨床で必要な基本的な運動学の知識や理解に乏しく、あまり臨床に役立てられない人もいると思う。
MMTは基本的には単関節の一方向に関する運動として、個々の筋、もしくは共働してはたら筋群の働きについて調べるのだろうけど、これが一致しているとも限らない。結局何をテストしているのか?ということにもなる。
複雑で理解し難いことは、単純な要素に分けて理解し考えてから再統合することにより、全体の理解につなげることも一つの方法であるが、MMTはむしろ実際の運動からはかけ離れているので、そこから脱却するのが難しくなると思う。
実際の運動は単関節運動であることは殆どなく、殆どの動きは連続三次元である。
MMTの呪縛から離れられないと、どうしても運動を二次元でとらえてしまいそこから脱却するのは難しくなるのでは?
筋肉自体も二関節またはそれ以上の複関節にまたがって作用するものが多く、むしろ単関節筋は少ないし、昔のロボットみたいな動き方は実際には殆どない。
正確なテストのためには「代償運動」にならないようにする必要があるが、実際の運動はむしろ複合的で代償運動に近い場合が多い。
連合反応はMMTでは排されるが、実際の運動は連合的、複合的であり、部分的な小さい運動にも全身が関係する。
上腕二頭筋も三頭筋も、大腿四頭筋もハムストリングスも、前腕の筋も下腿の筋も主要な部分は二関節筋であり、実際の筋肉の殆どは二関節筋やそれ以上の複関節筋で、動きも当然複合的である。
拮抗筋は拮抗するだけでなく共同して働く筋でもある。同時収縮や共同収縮の場合、拮抗筋が相反する方向に力が入れば、力が入るのに全く動きにならないが、共同して補助する働くことにより、強い力を発揮する作用もあるし、目的に合った適切な運動を補助する働きもある。
例えば前腕の屈曲を考えた場合、上腕二頭筋に対して上腕三頭筋は拮抗して屈曲を妨げるが、この拮抗筋の働きがなければ、上腕二頭筋は十分に作用せず、屈曲の力も弱くなるし、他者がもしくは固定物などで保持したり固定しなければ共同運動になってしまい、肘関節の屈曲だけの働きは不可能になる。
筋力があるのに動かせない。テストの点数は1?
拮抗しているだけでは収縮はあっても、重力にも検者の抵抗にも抗することはできず、4~5以上の筋力があっても1になってしまうという問題もある。
しかしテストの中にはそうした観点は入っておらず、実際には観察でかなりわかることではあるが、観察で得たことはむしろ主観的な見方として排除され、臨床に役立つ知識や技能には役立てられない恐れがある。
こうした問題に気づいたのは学生のときであるが…
OTの学生の頃の私は肩甲骨のリトラクション、プロトラクションの動きができなかったのである。内転(僧帽筋中部線維、大小菱形筋)?外転(前鋸筋、小胸筋、僧帽筋上部線維)かな?よくわからんけど。
自分はそのような動かし方がほぼ全くできないので、できなくても当たり前と思いこんでいた。鼻の穴を膨らませたり、耳を動かしたり、足指を別々に動かしたり、できる人とできない人がいるが、そのようなものかと。
この動きを上手く利用できなければ、投球やクロールで泳ぐなどの肩を大きく使う運動は殆どできない。私は実際にそうしたことが極度に苦手だったのにその理由がわかっていなかったのだが、その一つの大きな要素はそうしたことだった。
PTの人など運動が得意でその延長でセラピストになった人も多いようだけど、むしろ運動が苦手な人の方が向いているかもしれない。スポーツ選手としては優秀でもコーチや指導者などに向かない人がいる。できる人はなぜできて、できない人はどうしたらできるようになるのかわからず、考えてもこなったような人は向かないだろう。
もちろん私は身体的には「健常者」で運動麻痺はなく、ちゃんと神経はつながっているし筋肉も収縮するのであるが、力を入れても共同収縮、拮抗作用になって動かせない。従ってMMTの評価としては1になる。筋力はそんなに強くないにしても十分あるのだが。
要するに上手く神経が使えておらず、必要な力を入れて不必要な力を抜くことができず、無駄な力ばかり入ってしまう。
原因はよくわかった。
要するに精神疾患の症状である。動かせないのに、むしろいつも力は入っており緊張している。
リハ学院に入った頃は、精神病は随分良くなっていたのだが、私は早期から重症だったので、幼児期から身につけるべきことの多くが身についておらず、良くなっても大人になってからも中々身につかないことがある。それ以前にその必要性にも気づかなかったのでだが。
実際に精神疾患の人を見ているとそのような人は多い、というより殆どかもしれない。肩を動かそうとしても体幹や別なところも力が入って動いてしまう。腕も一緒に動いたり、顔まで力が入ったり。
当然のこと、普段も無駄な力が入りがちで、肩こり症にもなっているのだが、しばしばというより大抵は自覚もない。酷い人の方が却って自覚しにくいかも知れない。
稀ではあるが、肩甲骨の挙上(肩をすぼめる)ことができない人もいる。
若い女性なのにプロレスラーみたいに肩の筋肉が盛り上がっているのに、力が入るばかりでむしろ抜くことはできず、上手く動かせないのである。筋肉は身体を動かすためにあるのだが、むしろ緊張し動きを邪魔するための筋肉になってしまっている。
そういう人は書痙、振戦も酷かったが、やはり肩こりにも肩に力が入りすぎていることにも自覚はなかった。震えないようにすれば余計に無駄な力が入ってしまい、却って震えてしまう。
私は身体障害のリハは殆どできないが、こういった中枢の問題はなく、精神的な緊張が身体にも現れ、様々な支障をきたしている人を治療するのはもちろん得意中の得意である。
医学的な基礎知識はそれなりに役立っているけど、勉強不足と言えばそのとおりだが、正直なところOTになるための勉強は殆ど役には立っていない。
個人的に師事した心理療法の師匠の教えと、自分自身と患者の観察、洞察・理解によりわかってきたことである。
自分のことをついつい語ってしまうが、話を戻すと…
MMTは5段階評価とは言え、検者の主観によって判定するものであり、データ化できるわけでもなく客観性にも乏しい。抵抗に抗してと言ってもその抵抗の強さが問題でもある。などなど様々な問題も指摘されているが…
実際のリハの場面で必要な場合があるにしても臨床には役立てるのは難しいのではないだろうか。
運動の基本は…
階段を昇るにも、自転車を漕ぐにも、立ち上がるにも、股関節伸展、膝関節伸展、足関節伸展を同時に行う。
それらの筋の組み合わせ、収縮のバランスで実際の運動は行われている。
実際には重力は除去できないし、一定の方向(鉛直?地球の中心)に向かって一定の法則に従って作用している。
もちろん実際には重力の方向は鉛直に決まっているし、質量が決まっていれば大きさも変えられず、重力に従うか利用して、あるいは抗して運動するしかない。
たいていの日常生活における運動は、立っているか座って行っている。
そうではない運動は、実際には水泳などのスポーツや、ベンチプレスみたいなトレーニングとか美容体操くらいで、一般人の日常生活ではあまり必要がない。
MMTをやる時のように、肢位を変えて重力を除去したり、(身体に対して相対的に)重力の方向を変えて運動するなんてことは殆どない。
それを理解することは訓練に役立つことはあるだろうけど。
しかしMMTのように肢位を変えることにより重力の方向を変えるという発想を身に着けてしまうと、むしろ重力の働きを理解するのは難しくなってしまうの可能性がある。
一度観点や発想をリセットして、日常生活では重力の方向は決まっていることを前提として考え直し観察できるようになる必要がある。
MMTをやってはいけないわけではもちろん無いし、必要な場合もあるだろけど、学生のうちからそことをばかりやっても、臨床的な応用が効かない知識の蓄積になり、むしろ運動学的理解の妨げになってしまうのではないかと懸念する。
繰り返すが臨床の基本は観察であり、テストはむしろそのための補助に過ぎず、テストの結果をいくら積み上げてもそれだけでは評価にはならない。
テストよりも臨床観察を身につける方が大事で、臨床的にも応用が効くはずだが、そうしたことは少なくとも私の知る限りでは、複数の学校のいずれもPTはともかくOTでは殆どやっていなかった。
ここでお題を
立ち上がりや階段を昇るにしても、下肢の運動でとても重要で頻度が高く、大きな力を出す必要がある動作は、股関節を伸展させると同時に膝関節も伸展させる運動である。
自転車のペダルを踏むにしても、身体は持ち上がらず、その代わりにペダルが下に下がるのだが、基本的には同様の運動だ。
しかしそのように股関節伸展と膝関節伸展の同時に作用する筋はない。
この時、力を使うのは大腿前面の筋、大腿四頭筋(主に大腿直筋?)であるが、それは膝関節には伸展に働くが股関節は伸展ではなくむしろ屈曲に働く。
しかしなぜ大腿四頭筋を最も使うのか?
四頭筋に力が入ると、股関節の伸展に働くハムストリングスや臀部、股関節周囲の筋に対して拮抗筋として作用するのに。
逆に椅子に座るなどの動作も、関節の動きとしては、股関節は屈曲し膝関節も屈曲するので真逆になるけど、やはり同様な筋肉の使い方になる。
単関節筋だけに着目すれば、短縮性収縮と伸張性収縮の違いになるが。
これには重力が大きく作用するけど、もちろん立ち上がる時にも重力は同様に作用している。
当たり前だけど筋肉は伸びる方向に力を発揮することはできない。
等張性収縮、等尺性収縮、短縮性収縮、伸張性収縮などの運動学の概念をきちんと実際に則して理解しておく必要がある。
もちろん言葉を知ってるだけでわかった気になってはダメだ。
こうした事象をきちんと十分に理解した上で、立ち上がりや椅子に座る、階段の上り下りや自転車を漕ぐなどの運動を、きちんと明確に説明できる人はOTやPTにも実は少ないのではないか?
人間工学とか、スポーツの専門家や指導者なんかも同様だと思う。
もちろん皆ではないが、そういう人が意外に嘘を平気で言うことがある。
要するにわかっていないのに専門家のつもりになって間違ったことを言うから嘘になるわけだが、違和感があっても自分をごまかしたり。
私の知る限りでは自転車関係の人はかなり酷いと思う。
ペダル漕ぐなんて運動は、機械的に決定づけられており一定の方向にしかできないのだが。自転車は単純なだけに1つの要素がいろいろなことに関係しており、無限に複雑でもあり難しく、だからこそ面白いのだが。
データをとるのも速度以外、事実上殆ど不可能だけど、習熟すれば自分で試して体感や経験で知ることはかなりの程度で可能である。
自分の身体に聞け、感じて考えろ、ということだけど、これまたけっこう自分で自分をごまかしたりもしがちである。人間の感覚はかなりの敏感であると同時に無自覚に歪曲もされやすい。
自転車となるとついつい語ってしまい、話がズレたが…
よくわからない人は、学生時代に運動学を習った先生にでも聞いてみたら良いけど、もしかしたら授業でも殆ど習っておらず、先生でもあまり説明できないかも知れない。
俺は十分ではないにしてもこうした運動について一応説明できるつもりだけど、専門でもないし正確に記述するのはやっぱり難しいと思う。
--------------------
今回もまたOTの皆様からは反感をかったり、お叱りを受けそうな記事ですが。
私は精神疾患のセラピストで、とっくの昔にOTは辞めており、身体障害のリハは正直あまり関心もなく、殆どやってもいないので間違いや不適切な記述もあると思いますが悪しからずご容赦願いたい。
それでも敢えて書いた主旨や意図をご理解頂き、何かの参考にして頂ければ幸いです。
叱らないで 青山ミチ
https://www.youtube.com/watch?v=XSKu9u3W0nY



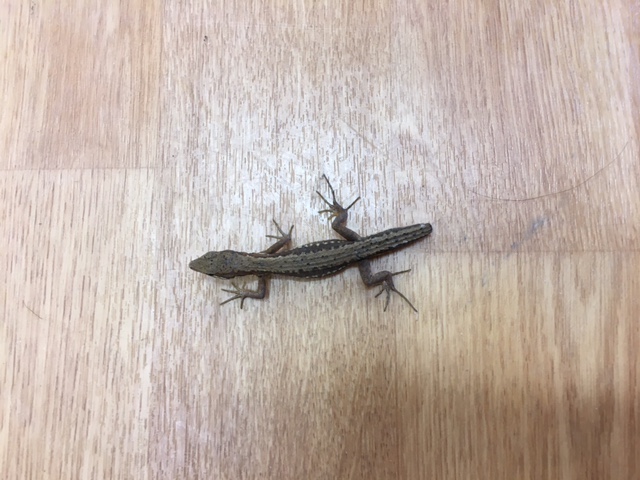

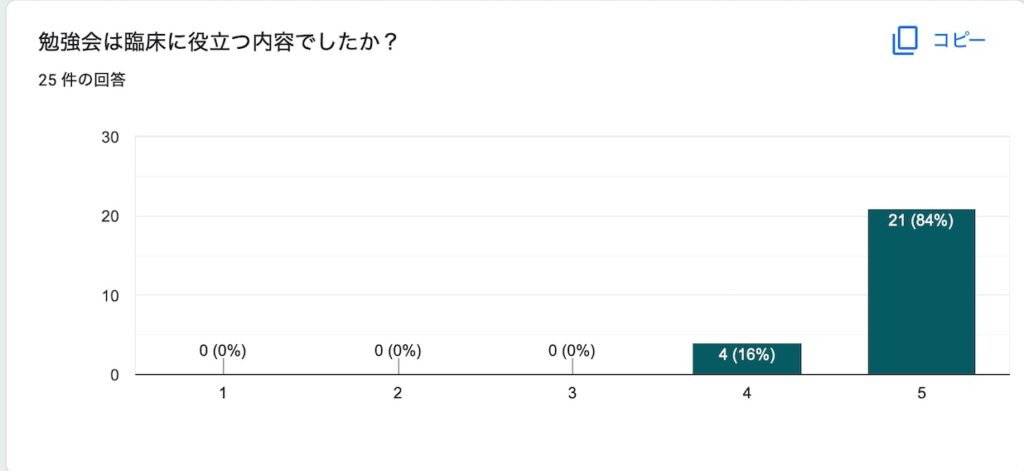



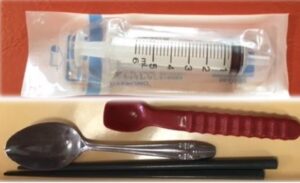






最近のコメント