もう3カ月程前になるが中井久夫さんが亡くなられた。日本の精神医療の良心とも言われていた精神科医である。
私はもちろん面識はないし、著作や翻訳書を通して知っているだけであるが、初めて知ったのはもちろん精神医療を志すより前、ただの患者の頃で「現代精神医学の概念」を読んだ時だから高校時代か少なくとも大学1~2年の頃には知っていたことになり、これまでに全部ではないが著作の殆どは読んでいるはずである。
中井さんが神戸大学を退職した後釜に教授になった人は認知症が専門の人だし、さらにその後継者はハッキリ言ってどうでも良いような…、他大学も同じようなもんだが。
弟子や後継者と言えるような人は安克昌さんの他にはいなかったようで、その安さんも阪神大震災の対応の労苦もあってか39歳の若さで早世してしまった。
傲岸不遜、高慢と思われることは百も承知であるが、彼の著作を読んでいると正直言って教唆したいことがいろいろ頭に浮かんでくる。エッセイなどは面白くて得るものも少なくないのだが、専門の精神医療に近づけば近づくほどそうなのだが。
そこらの精神科医や臨床心理師などとは話が通じるとは到底思えないが、中井さんならわかって頂けるのではないか?といったことである。
結局それを伝える機会はなくなり残念ではあるが、残念なのは私ではなく中井さんの方かもしれない。もちろん実際にはわからないし、タラレバのことを言ってもしょうがない。
実は連絡を取ろうかどうしようかなどと随分迷ったことがあり、実際に連絡を試みたときは既に高齢のため身体の方が弱っていたようで、出版社や大学には取り次いではもらえなかった。もっと早く、とも思うが仕方がない。そういうもんなのだろう。
何事にも、特に人間関係においては積極性に乏しいのが私の欠点であるが、他者と関わったり話したりすることには、なるべくためらわずに積極的に行ったほうが良いと皆さんにはアドバイスしておきたい。今は幸いにしてメールやSNSなど使いやすい手段もある。
ギリシャ語を3日でマスターしたというほど頭がよく人間的にも優れた人に、俺のような精神病で怠け者でボンクラのバカが教えられることなど、もちろん唯一つしかない。確かな治療法を持っておりそれを実践し結果も出しているということである。
それしか取り柄がないとしても、やはりやっていなければわからないことも、経験しているからこそわかることもあるのだ。
そもそも私の読書は著作を読んで何かを学習するということは殆していないしできない。理論を学習してそれを適用しようとすることもほぼ無い。従ってテストの点を取るためのような勉強もほぼしたことがない。
自分にとっての読書は端的に言えば自が考えたことやわかったことについて、他者の意見や考えを聞いて確かめるためだ。それしかできないのでしょうがない。
昔から私は活動的ではないが、実践を通して経験から学ぶことを子供の頃から心がけ、知識を当てはめただけでわかったような気にはならないようにしてきたつもりである。
それが良いとも一概には言えないが、勉強嫌いも必ずしも悪いことではないと思う。
「事実の子たれよ。理論の奴隷たるなかれ」
私の治療のことを知って頂けたら大いに関心を持ってくれただろうし、大いに賞賛または賛同し驚喜して頂けただろうとも思うのだが、正直言ってその自信はあまりない。少なくとも確かな結果が出せる治療法であり、治療法に自信がないわけではない。
中井さんが主治医だった患者が私の所に来たことはある。
以下はたぶんに俺の推測に過ぎず、穿った見方かも知れないが…
彼は統合失調症(精神分裂病)を含めて、精神疾患は脳の病気ではなく精神の病気であり、原因は生物学的な遺伝による脳の特質や偏差ではなく、心因、環境因、家族因だと言いたかったような気がしてならない。それが全てではないし確かなことは言えないにしても。
もちろん今の精神医学会で受け入れられるわけはないし、誰でもわかるように明確な根拠を示せるわけでもないけど。この点ではやはり俺の方が知っていることは多いと思う。
彼はそのことを伝えるのに明言はせず、いつも寸止めというより尺止めしていたような気がしてならない。
だからこそ、日本で最高の精神科医、精神科医の良心と言われつつも、あまり彼の考えは受け継がれ難いのだろう。
著作は多く、著作集もあるし今もそれなりに売れているようだが、多分読者の多くは精神科医や心理療法関係者ではなく、一般インテリ階級だろう。
惜しいことであるが、また時代は巡り巡ってやってくるかも知れない。
中井さんは晩年カトリックに帰依したという。
この点でも俺は一応先輩だ。先祖代々(明治時代からだけど5代目)カトリックなので生まれた時に洗礼を受けているので。自分自身の傲慢を戒めるため、といった理由のようだ。私ももちろん自戒が必要である。
私は英語も苦手なので、中井さんの翻訳のお陰でサリヴァンだけでなく精神医学の重要書物を読むことができた。他にはフィレンツィ、バリントなど。これはとても有り難いことであるが、それらの書物も品切れ絶版になりつつあるので、まだ読んでいない人はぜひ手に入れて読んでみると良いと思う。今なら古本もそんなに高くない。
とりあえず「現代精神医学の概念」から始めて「精神医学的面接」そして理論的なことを知りたければ「精神医学の臨床研究」あたりを読んでみるのがお勧めである。「臨床研究」はリハビリ専門学生の頃に読んだと思う。最初は取っ付き難かったが、理解が進むとむしろ自分が仮説的に考えていたことが明確に示されていることがわかり膝を打って驚喜した。まだ精神医療を志すよりもずっと前からそのようなことが書いてあるのでは?と期待していたのである。
他にはフロム=ライヒマン、サールズなど。
意外にもサリヴァンはDSMの原型も作っている。彼は戦争に反対であったが、政府の求めに応じて兵士を選抜するためにチェックリストを作ったのである。「興味関心のある内科医であればおそらく認識できるだろうという点を目指して作成された」という程度のものであったが。
その後DSMは肥大化し普及し当初の理念や主旨や目的とはおよそかけはなれたものとして独り歩きして広まり普及し「専門家」に運用されただけでなく一般人にも広まった。
その割には正確には内容が伝わらず恣意的に使われており、サリヴァンの作った原型を元にDSMの初版を作った人も後悔していたはずである。
どういうわけだか最近になって、サリヴァンの入門書的な本も訳出されている。
「個性という幻想」講談社学術文庫
文庫なので割に安いし、訳も読みやすい方である。冒頭部分はサリヴァンの入門の入門とも言えるが今まで訳出されていなかった。それに既に入手困難となっている著作のうち4つの論文の新訳が加えられている。まずこのあたりから読んでみるのもよいだろう。
「ハリー・スタック・サリヴァン入門: 精神療法は対人関係論である」F・バートン・エヴァンス3世 創元社
これまでサリヴァンの入門書的な本は何冊が出ていたし邦訳されているのもあったのだが、内容や訳があまり良くなかったりしてお勧めできるものはあまりなかった。これは良い方だと思う。
中井さんもサリヴァンも今の精神科医や医療従事者にとってはもはや過去の人に過ぎないのかもしれない。しかし、優れた人の洞察・理解には普遍性がありいつの時代も有益である。
もはや昭和の(旧)精神分裂病を知る人も少なくなってきた。統合失調症と名称が変わっただけでなく今世紀になる前後からずいぶんと病像が変わり、同じ病気とは言えない程である。私は元々疾患単位を認めない立場なのだが。
もっとも(旧)精神分裂病と言えども近代の病であり、エミール・クレペリンによる早発性痴呆の提唱は1893年であり、オイゲン・ブロイラーの精神分裂病は1916年、野口英世のスピロヘータの発見は1918年である。
結局のところ(旧)精神分裂病は高々百年程度の歴史しかなかったことになる。
近世以前はそれと似通った病気もあっただろうけど、おそらく憑依精神病が主な精神疾患である。
憑依なんて言うとおよそ前近代的なのは当然としても非科学的と考える人も多いだろうが、そうした現象があったことは間違いなく厳然たる事実である。今でもあることはある。
私はそうした歴史や現象を理解せずして精神疾患の原因論を語るべきではないとさえ思う。世界には科学の対象にならないことの方が多いのである。
「愚者は経験から学び、賢者は歴史から学ぶ」
私は両者から学びたいと思うが、後者を重視すべきお年頃になった気がする。
--------------------
もはや若い人はあまり知らないと思われる昭和歌謡のカバーですが、こういうの好きな人も知らない人も聴いてみると良いと思う。「利理鈴まりりん」で検索すると40曲以上出てくる。
「昭和も遠くになりにけり」
この人は変な癖がなくて妙に上手い!魂が入っておる!?という気がする。
昔はこういった歌謡曲は好きではなかったが、ジジイには今風の曲も歌い方はあまり馴染めないのだ。
なぜかうるうる感動的、なぜか何度聴いても飽きない。
キーボードの人のハモリも良く、ボーカルが良いと演奏も熱が入るようだ。
歌が上手けりゃ見た目はどうでも良いのだが、たぶん人柄も良いのだろう。
ごむてつ君に励ましのメールを出そう!
auchida@msi.biglobe.ne.jp






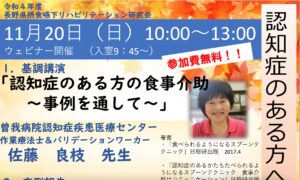





最近のコメント