むかし大学教師だった頃、時々学生と一緒にスキーに行った。もちろん最初はできないから経験者の学生に教えてもらったのだが。
生徒が先生に教えるわけで気後れもあるし仕方がないことだけど、ハッキリ言って教え方が下手なのである。質問しても殆ど応えられないし。
教えるのは当然面倒だし、そんなことより自分が行きたいコースで滑りたいように滑りたいのはよくわかるので「もういいから」と言って独りで練習することにした。初心者っぽい人の中でも自分よりは少し慣れていそうな人を見て真似したりして。
1回目は学生に教えてもらったけどそれからいろいろ考えて試して、2回目には全く初めての人には教えていた。1日中苦労しただけに文字通り一日の長があるのだ。
何かを習得する時にはそれを他の人に教えるにはどうしたらよいかをいつも考えている。
今は違うかも知れないけど当時は、初心者はボーゲンと言って足をハの字にして内側のエッジを立てるようにしてコントロールするのだが、これが最初はなかなか要領を得ずだいぶ苦労した。
股関節を股関節の内旋と足首の外反を同時に行うのは普段の生活には殆どないし初めてだと難しいので、どうしても内反しがちになってしまうし、外側のエッジを雪面に引っ掛けやすく、これが転ける原因にもなる。
学生には、
「とにかく慣れないうちは見た目を気にせずにとにかく大股開きにすると良い。そうすると足関節は自然に外反し内側のエッジが使えるので、制御しやすいので多少急な場所でもコントロールできるしすぐに止まれる」
「大股開きにすると脚がどんどん開いてしまい股裂きの刑になりそうな錯覚があるけど、実際には外転させると外旋にも内旋にも自由度が広がりむしろ内旋させやすくなるので自然にできると同時に足関節は内反するので、内側のエッジが立つので実際にはむしろ逆で股裂きにはならない」
「ついでにどの筋をどのように使っているか、どのように働いているかなども考えてやると良い」
てなことを話していたら、学生には怒られてしまった。
「せっかくこんなところまで遊びに来たのに勉強のことなんか考えたくないっ!そんなこと忘れて楽しむために来たのに!」などと宣う。
実演しながら教えているのだからわかり難いということはないはずだが。
俺としてはすっかり驚いてショックを受けてしまった。
趣味やスポーツや生活の身体の動きなど様々なことが仕事に生かせるし、また逆に専門的な知識や経験を日常にも活かせることがOTの魅力だし面白さだと思っていたので。
精神科でも基本的には同様だ。
どうも専門的な知識や臨床の実践と、日常生活や趣味や遊びは別と思っているか、統合できていない人が多いような気がする。
PTの人はスポーツをやっていた人や体育系の人が多いと思うけど、どちらかと言えばスポーツとリハビリの仕事は別と考えていたり、あるいはスポーツの方に軸足があり、その延長でリハビリを考えている人が多いように思う。それだと臨床的な理解や方法にはなり難いと思う。
スポーツの指導やコーチをするのとリハビリとでは全く別物だと思う。初心者どころか障害がある人が対象なので当然だろう。コーチや指導者は初心者に教えるのはまだ良いとしても、運動神経が極度に鈍い人に教えるのは苦手ではないだろうか?
ギターやベースをやっていると日常生活では殆どないような手指の使い方をすることが多い。
ギターの持ち方や構え方、姿勢なども手指の動きに随分影響するもので、始めた頃はもちろんそんなことがわからないので変な癖を身に着けてしまったり。いろいろ事情もあってそうならざるを得ないところもあったが、昔はビデオはなんかないし教則本なんかもろくなのが無かったし。
例えばギターを上から見て身体と平行に構えていたけど、むしろヘッドを前に突き出すようにして斜めに構えた方が指はだいぶ開きやすく動きやすい。
これでもOTの端くれでありながら、正直言って何十年も気づかず最近気づいたこともあるし、もちろんまだまだまだ発見することもあるはずだ。
他の楽器なんかでも良いかもしれないが、ハンドセラピーをやるような人ならむしろギターは必須にした方が良いかと思うくらいである。
ギターの弾き方には実にいろいろあるし、手の使い方のバリエーションはものすごく多く、日常的には使わないことも多い。
日常的に使わないことなら、他のことやら臨床には役立たないのでは?と思うかもしれないがそんなことはない。いろいろ体験してみて初めてわかることも多いはずだ。
だいぶ前にOTの重鎮の方が「手のかたち、手の動き」という本を書いていたが、ギターだけでももう一冊書けそうだ。
身体的なことに関しては、こうした趣味を治療に活かす、専門的な知識を趣味などに活かすという意味では、私はそもそも身体障害の治療はやっていないので必要性も乏しかったし、もう遅きに失するかもしれないけど。
というわけで唐突だが最近私はドラムを始めた。
今さらバンドをやったり人に聞かせるようなこともないだろうし、治療に活かせることもあまり無いだろうけど、目的は老化防止と精神・神経の健康のためである。
ガキの頃からギターやベースは一応弾いてたし、下手ながら一時期バンドをやってたこともあるけど、あまりに運動神経が鈍く不器用でリズム感が悪いので、畏れ多くもドラムには手を出さなかったのだ。
今から思うとだからこそやるべきだったのだが、長年そこまで思い至らず、もっと早く昔からやっておくべきだったとつくづく思う。
音楽をそれなりにやるとか歌を上手く歌いたいなら、メロディ楽器とコード楽器とリズム楽器はそれぞれ一応はやるべきだろう。
「だんだん良くなる法華の太鼓」
「心に太陽を、唇には歌を、体にはリズムを持て!」
精神疾患を発症したり老化が進むと顕著なのはリズム感が損なわれることである。
私の場合は両方が原因であるが、大抵の場合無駄に力が入ってしまいうまく抜くことが下手になっている。当然疲れやすいし。
ドラムは脱力に始まり脱力に終わると言ってもいいくらいだ。たぶんね。よく知らんけど。体力も必要と言えば必要だが、意外にそれほどでもなくむしろ中高年に向いた楽器だと思う。とりあえず練習用のパッドとスティックがあれば良いし、あまりお金もかからないので思ったより手軽に始められる。
ほぼいつでもどこでも練習できるので、歩きながら「くいだおれ人形」のように練習している。授業中でも音を出さないように手足を動かしているのがバレないように机の下でやれば練習できるぞ。頭の中だけでもイメージトレーニングができるが、そういうのがけっこう重要だったりする。
我ながら日々上達が見えるので面白いし、曲に合わせて手足を動かすだけでもけっこう楽しい。
やっぱりいろいろな手足の使い方をするし、全体の姿勢や呼吸なども関係するので勉強になる。
俺は無理だが、スティックのコントロールだけで分厚い本くらいは書けそうだし、実際にそういうのもある。
始めてみて直ぐにわかったことだが…
私は酷く運動神経が鈍く、不器用であることは重々自覚しており、中々改善せず半ば諦めてもいたのだけど、特に左手の使い方が極度に下手だ。もちろん右利きだからというのはあるが、それにしても、である。
左手はなぜこんなにも不器用で言うことを聞かないのか?改善するにはどうしたら良いか?ということは今まで殆ど考えたことがなかった、というかむしろ避けていたのだが…
日常生活では特に困るわけではないし、人間苦手なことはあまり認めたくないし克服するよりも無視したり避けがちである。疾病否認や病態否認もそうしたことの延長ではある。
具体的にはスティック(バチ)でドラムを叩く時、手首の動きに関しては、手首の屈曲、尺屈、それと回内を主に使うが、私の場合特に左手の回内回外の動きが極端に悪いことに気づいた。
スムーズに速く正確に回内回外させることができず、特に肘をほぼ90度の状態で肢位をほぼ保ったままやると、前腕部の筋に無駄な力が入ってしまい、共同収縮も多く動きを阻害しながら動かすことになってしまう。
要するに回内回外の分離運動が特に下手なのだ。もちろん統合的に動かす必要があるのだが、主な問題はそこだった。他の人にはどこまで当てはまるかわからなけど。
そこが克服できればまた別の問題がネックとなるのだが、でもそれで次のステップに進める。
そういうわけで、とにかく回内回外だけ訓練してみたら、左手の使い方は飛躍的に改善した。普段の動作も少し器用になり、手先の巧緻性もいくぶん改善しギターやベースも弾きやすくなったくらいである。
辞めたとは言えOTの端くれなのに、こんな簡単なことになんで今まで気づかなかったのか?と唖然としたけど、日常生活では特に困らないしドラムをやらなければ多分一生気づかなかったに違いない。
それでレギューラー・グリップ(ジャズなんかで使う持ち方で、回内を主に使う)でも下手だけど一応は叩けるようになった。そんな奇妙な?持ち方で叩くなんて最初はとても考えられなかったのだが。
たぶん最初からそこそこできる人と、私のようにとてもじゃないができない人がいると思う。
他の楽器に比べて「あんなの人間業じゃない!俺なんか出来るわけがない!」と思うことが意外にできたりして、イライラして嫌になったりすることは少ない。ギターを教えたがる人は多いが、ドラマーがあまり人に教えたがらないのは、多分ドラムが一番面白いからではないか?という気がする。
到底無理だと思うことでも、特に障害でもなければたいていのことはそこそこのレベルにはなれると思う。いきなりできるようになろうとしても無理でも、多少は時間はかかっても急がば回れで、なるべく基本からプロセスを踏んでやっていけば。
できる人がそれなりにいることなら、多少の向き不向きはあっても自分にはできない、無理だと思う必要はない。
と、偉そうなことを書いているが、実はまだ本物のドラムセットは触っていない。そのうちスタジオに行って練習してみるつもりだけど。
「講釈師、見てきたような嘘を言い」
昔、若い頃ちょっとばかりおイタしたことはあるけどな。
脳卒中右片麻痺の患者さんなんかに「利き手交換」と称して碁石の玉やら豆粒などお箸つまんでただ移動させる訓練など、今どきやるOTはたぶんいないだろうけど…
それが悪いというわけではなく必要もあるだろうけど、わざわざ訓練室に来てセラピーの時間を使ってやるものではなく、OTとしてやるならどうしたらそれが早く簡単に上手くできるようになるか、そのポイントを絞って指導・訓練するべきだと思う。
精神科の患者さんなんかは酷く不器用な人が多いが、ただActivityをやるのではなく、それが上手く出来るように基本から指導すべきだろうし、それが出来るのがOTの専門性というものだろう。
人によってはやはり苦手なことはやりたがらないし、抵抗を示す人もいるだろうけど、良い指導ができればわかってくれたり受け入れてくれる可能性が高いし、それで結果が出せれば精神的にも良い影響があるはずだ。
私はOTはもう辞めたけどセラピーでは神経そのものの状態や働き、使い方(というより無意識による使われ方)から改善できるように指導している。
ドラマーは基礎練習だけでなく、上達のために運動や体操をしたり、準備体操やウオーミングアップをするのが普通だ。
指導のポイントとは弱点・欠点を目ざとく見つけてそこを指摘してやらせるのではない。それだと下手ながらも一応できていたことが余計にできなくなってしまい、嫌になったりやる気がなくなりがちになる。
ポイントとはここを変えればあっちもこっちも良くなるからはるかに上達する、あるいはとりあえずここを改善すればこういうことができるので、その次にここを改善すれば…といったことであろう。
私は泳げなかったので中年の頃に教えてもらったり練習して何とか泳げるようになったのだがそうしたことを痛感した。結局教えてもらっても殆ど上達せず、自分でやり方を理解して訓練法を考えたことが上達につながったのだが、それも一応OTだから可能だったのかもしれない。
昔は体育や音楽や美術の教師などはロクに教えることができず、ただやらせるだけだった。酷いやつは水泳なんか棒で突っついたりなんかしやがって。今でも恨みが怒ってくるぞ!
今どきはきちんと教えてくれる先生が多いのだろうけど、それにしてもプロとして本当に教えることができる人はどのくらいいるだろうか。
だんだんわかってきたことは、自分が苦労して習得したことことや、大抵の生徒が苦手でも自分たちは得意なことを、生徒が簡単に上手くできてしまったら自分の立場やプライドが保ずむしろ困るわけで、自覚しているかはともかく差別化選別主義が根底にあるのだろうと思う。
そのためきちんとした指導法を考えたりすることを怠っていたのではないかと思う。
そういうつもりはないだろうが、殆どの先生がそうだったから。生徒にマウントとってもしょうがない。
俺なら上手く教えて生徒が皆、俺を楽々超えてしまうことにプライドを持つけどな。教師はできることより、教えることが仕事だ。音楽の先生はプロのミュージシャンじゃないし体育の先生はオリンピックや大会に出るわけではないし、もちろん殆どの生徒もそうだから、いかに上手く楽しめるか他のことにも役立てるかだ。
俺は優しく親切でサービス精神が旺盛なので、上述のようにスキーなんかも二回目には初めての人に教えたりなんかしていたわけだが。
ゴルフの練習場なんかでは教えたがり屋の嫌われるタイプでジジイである。ゴルフはやらないけど。
今は精神疾患の治療のことを教えたいのだが弟子はいないし、そもそも治療を教わる気がある人が殆どいないようなんである。これまた、だんだんわかってきたことは、精神科医や心理カウンセラーなんかになりたい人は掃いて捨てるほどたくさんいるけど、本当に治療をやりたい人は殆どいないということである。
それでメシが食えるとは限らないし、というよりとても難しいし。もっと言えば患者自身も本当に良くなる治療を求めていない。要するに『抵抗・防衛』ということだが、それを克服することを含めて治療なんだけど、それは患者側の問題でもあるがむしろ治療者自身の問題である。
今はそうでもないと思うけど、我々の世代だと音楽やスポーツや英語なんかも学校時代に何年もやっていたのに大抵の人は大してできるようにはならないし、できる人は自分がやりたくて教室に通ったり訓練や練習に励んだ人だ。
やっぱりリハビリの仕事もそうで学校は優秀な成績で卒業して資格をとっても、実際にできるようになるには自分から本を読んだり講習会に参加したり、学習して身につける姿勢や努力がないとダメだし、何事もセラピーに活かせるようにフル活用し、また専門的な知識を治療以外の様々なことに活かせるように心がけた方が良いと思う。
日々の臨床の中でも自分で自分を訓練し学習できる人と殆どできない人がいる。精神科なんかは特に経験が逆効果になっていることも多いから恐ろしい。
※追記
ところで最近、認知症のリハビリや評価に太鼓が使えるといったことがよく言われているようだ。
「認知症 太鼓」などで検索するといろいろ出てくる。
その辺は門外漢だし私としては何とも言えないのだが、何となく良さそうである。
実際にでかい音を出したほうがもちろん良いのだろうけど、当然のことウルサイのが難点である。ドラムの練習には一般に練習用のパッドを使うのだが、スネアドラムのスタンドにドラムの皮だけ固定して叩いたりもする。
それでもそれなりのお値段がするので、やはり100円ショップとかホームセンターで素材になるものを組み合わせて使うと良いかもしれない。スティックも一般的なものは1,500円くらいでそんなに高くはないのだが、Amazonなど探ると中華製の安いものも手に入る。
(92)嵐を呼ぶ男(石原裕次郎・笈田敏夫) – YouTube
いかりや長介の演技が秀逸でちょっと感動的
ドリフターズ加入前の志村けんもチラッと出てくる
ドラムすめには負けたくない。可愛いけど。目標は追いつき追い越せだ!
ごむてつ君に励ましのお便りを出そう!
auchida@msi.biglobe.ne.jp
もう禿げてるけどな
これ以上禿たら頭蓋骨が見えてしまう。








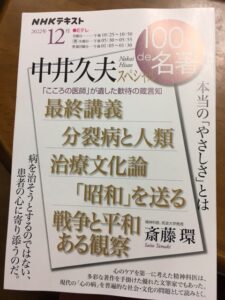

最近のコメント