
中島みゆきの「ファイト!」と 「宙船」をぜひ聴いてほしいと思います。
働いていると、いろいろなことがあるじゃないですか。
詳しく説明しなくてもツーカーで分かり合える人と出会えたり
頑張っている人の踏ん張りを見聞きして自分も頑張る勇気をもらえたり
一方で
胸糞悪いことも、理不尽なことも
一生懸命な人が辛い思いをするだけだったり
足を引っ張られたり、悪者にされたり
そういうのも、頑張ってるからこそ。なんだよね。
私は、いろいろな場所でいろいろなOTと出会ってきました。
私は頑張っている、信頼できるOT達を知っています。
同時に、なんちゃってOT達も知っています。
なんちゃってOTは、自分が困らないように立ち回ることしかしてこなかったから
自身では立ち回れているつもりでも、ハタから見たらバレバレです。
真っ当な人と真っ当な話はできずにOT人生を終えるしかないけど
それもその人の選択でその人の責任なんだよね。
大切なことは、自己表明なんだと思ってます。
なんちゃってOTをはじめとするわからんちんにじゃなくて、世界に対しての。
私はこうしています、こう在りたいですと、世界に対して、自分自身に対して、表明する。
(表明とは言葉だけじゃなくて行動も含めています)
だから、わからんちんにわかってもらう必要なんて全然ない。
ただ、わからんちんにも言った方が良い時もあるとは思う。
「私は表明した。あとはあなたの選択。選択した責任はあなたにある。」という意味で。
もしも、その人の中でアンテナがちょこっとでも立っていたら
今すぐには無理でも、後になって伝えられた言葉を思い出して真正面から受け止めてくれることがあるかもしれない。
以前に勤めていたところで
あんまり話をしたことがなかった(実は私はあんまり信頼していなかった)人から
「よっしーさんて、対象者や家族の悪口は絶対言わないものね」と言われたことがあって
びっくりしたことがあります。
どんなOT人生を送るかは、自分で決めて選ぶことができます。
そして、言葉にすることで、行動に示すことで、自身の選択を表明することができる。
変な言い方に聞こえるかもしれないけど、
表明すると、そして表明に足る実践を続けていると
状況が変わったり(本当にありえないような変化が起こったこともありました)
実現の機会に遭遇することが本当に起こりました。
これはどういうことなのか、わかりません。
神様が願いを叶えてくれたのか
世界が聞き届けてくれたのか
たまたまそういう巡り合わせだったのか
巡り合わせは実はたくさんあったのに気づかずに過ぎてきたことを自分が気づけるようになったのか
自分が変わったから周囲を見る自分の視点が変わって同じ景色を見ていても異なるように見えたのか
何が起こっていたのかはわからないけれど、
私の相手は私であって、わからんちんじゃないってことだと思う。
時には、闘えなくなることだってあるし、漕いでた手が痛くて動かせない時だってあるし
冷たい水の中でじっと耐えてることが最善のことだってあると思う。
でも、今、手応えがなくても先が見えなくても、奥歯を噛み締め涙を堪えても
それは、頑張ろうという志を持ってるからこそ
そう在りたいという願い、そうせざるをえない志を持っているからこその辛さ
その願いや志が崇高であればあるほど、そんな容易く実現できるわけがない。
だから、表明し続けないと。
肝心なことは、口先だけじゃダメ。
当たり前だけど。
だって、「自分は口先人間だ」って世界に表明してることになっちゃうから。
今、辛い思いをしながらも、頑張っている人たちに伝えたい。
頑張りが無駄になることは決してない。
望んだ結果になることばかりじゃないけど
真摯な努力は確実に自身の成長につながっているし
別の場所で頑張っている誰かがちゃんと見ていてくれてる。
仮に、誰にもわかってもらえず、本当に孤独な思いに潰されそうな時があっても
世界に表明しているのだから、それで良いのです。
そうやって、崇高な志や願いを実現するに足る実践力が磨かれていくように感じています。
時には休んでも
時には後退りしても
願いや志を捨てさえしなければ
状況を変えられるだけのチカラがつくか
状況の方が変わってくるか
いずれにしろ、機会は巡ってくるから
その時に十分にチカラを発揮できるように牙を研いでおく。
ハタからは沈黙と思われても、自分にとって雌伏の時期を過ごせば良い。
「るろうに剣心」の中で
「捨てたものは見つからないが、失くしたものはきっと見つかる」というセリフがありました。
正確には
「まあ しかし 長い人生 何かを失うコトは常につきまとうもの 捨てなければそれでいいんじゃ」
「失ったものは再び不思議と見つかったりもするが 捨てた物は再び不思議と拾えた例がない」
というオイボレのセリフのようです。
だから、頑張れ〜!
私も頑張る〜!
一見、悪いことに見える良いことも
良いことに見える悪いこともあるから
OT人生ってわからないものです。

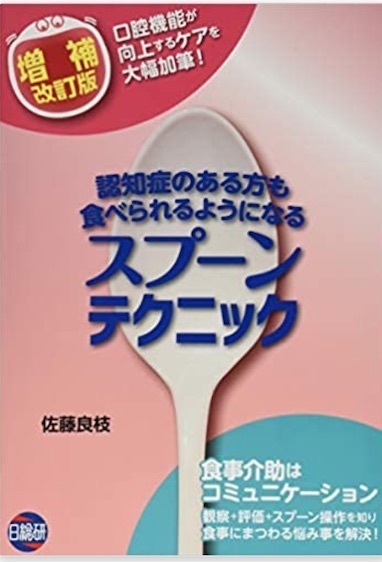



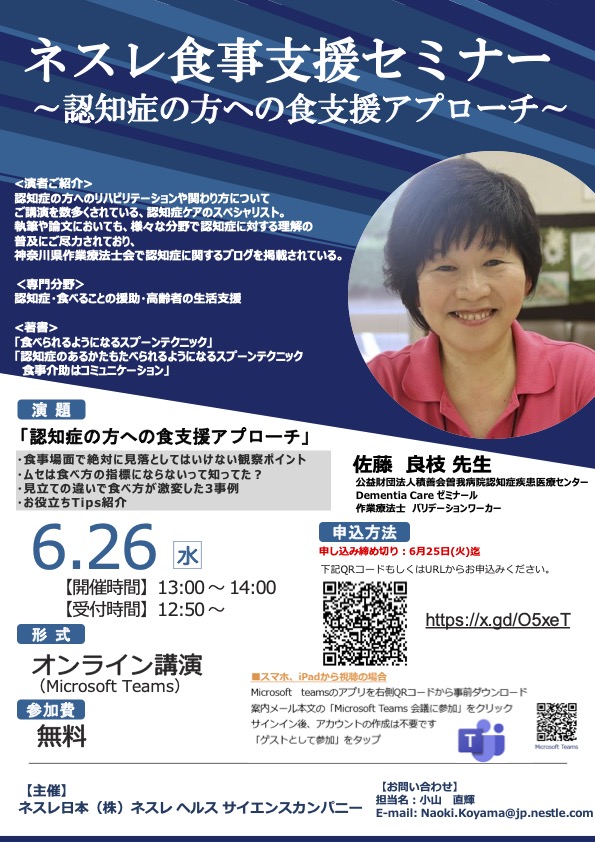






最近のコメント