
きちんと観察すれば
その方がどういう状態なのか、そのポイントを洞察することができます。
洞察するに際して、最も重要なことは考え方で
良いと考える姿勢から、差し引きマイナスで現状を見て「修正」しようとはしないことです。
その方が困っているところを洞察して「援助」しようと考えてください。
多くの場合に
「修正しよう」と考えて対応して逆効果になっているのです。
そのような考え方ができるのは、実は、
その方固有のポイントを洞察できていないからだとも言えます。
例えば
下肢が交差してしまうケースでも
状態像はケースによって、まったく異なりますが
きちんと全体を観察しないと
ただ、下肢が交差しないようにというポジショニングを設定してしまいがちです。
(そして効果がないのに、そのまま放置されて、対象者の状態のせいにされるという。。。)
ある方は
下肢そのものの筋緊張はさほど高くありませんでしたが
円背があって肩甲骨が外転・前方突出していて肩甲帯が不安定でした。
肩甲帯が安定するように肩甲骨〜上腕にかけて柔らかなクッションを、
膝下〜下腿にかけてクッションを設置したところ
下肢の交差そのものへは何の対処もせずとも交差することはなくなったということもありました。
別の方は
下肢を含めた全身の筋緊張が高く
下肢は伸展パターンをとっていましたので
骨盤を後傾させ股関節を屈曲させてからクッションを設置し
膝下〜下腿、上腕下にクッションを設置することで全身の筋緊張が緩和されました。
見た目は同じ「下肢が交差している」状態でも
1例目は肩甲帯の不安定さ
2例目は下肢の伸展パターン
というように、状態像は全く異なっていますから、当然、対処も全く異なります。
下肢の交差という、とても目立つ「見た目」があると
そこに注目して、修正しようとしがちですが
まず、常に全身、全体像を観察することが重要です。
1例目は
目立つ「見た目」にとらわれて
ポイントである肩甲帯の不安定さを見落としてしまいがちですし
2例目は
目立つ「見た目」にとらわれて
下肢だけを外転・屈曲させようとクッションを膝の間に詰め込んだり
必死になって屈曲させようとしがちですが
大抵の場合に、クッションを外せば一気にキューっと下肢が伸展内転してしまいます。
そうすると、全身が一層硬くなってしまうのです。。。
それじゃあ、寝ても寝た気がしないと思うのです。。。
見た目だけ捉えて表面的に修正しようとしても
効果が得られないどころか逆効果になってしまいます。
自分の気になるところだけをみて
表面的に修正・改善しようとするような在り方は
ポジショニングだけでなく
生活期にある方の食事介助でも
認知症のある方の生活障害やBPSDへの対応についても
散見されるパターンです。
私がよく
「同じコトが違うカタチで起こっている」
と言う所以です。







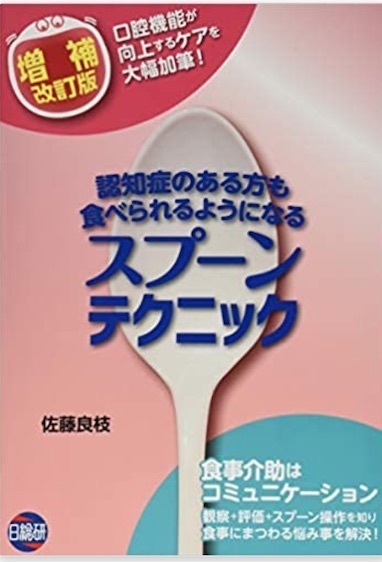


最近のコメント