
「刺激がないと認知症が進行する」
って言う人、いますよね?
認知症のある方にいろいろなActivityを提供する人もいるでしょう?
「刺激があった方が進行を予防できる」
「私と一緒にやるから大丈夫」
って言う人もいるでしょう?
この言葉は
構成障害のある方には禁句なんですけど
認識できていない人がまだまだ多いんだなーって感じています。
よくよく観察していると
隣で一緒にやって見せてるのに、どうしても違うことをしたり
Activityの最中に突然怒り出したりする方に遭遇したことがありませんか?
認知症だから怒りっぽいんじゃなくて
怒るという表現でしか、気持ちを表出できないだけで
怒らせるきっかけを作っているのは善意の職員というパターンが結構あります。
このことは後日改めて詳述するとして。
刺激がないから認知症が進行するわけではありません。
やればいいってもんじゃないのです。
私はもっと正確に
「刺激があれば良いわけではない」
「適切な刺激がないと、認知症が進行する」
「適切な刺激でないと、不安感や混乱から生活障害やBPSDが増悪する」
と言い換えたいと思います。
認知症のある方をよく観察している方なら
楽しいはずのレクの後で
混乱したり不安になったりした方を知っているはずです。
作品は仕上がったけど
あれこれと指図するのは職員で
認知症のある方は必死になって言われた通り、
介助された通りに手を動かしているだけ
ということに気がついているはずなんです。
心のどこかで
「これは私が『作らせた』もので、この方が『作った』ものじゃない」
こんなやり方で本当にいいんだろうか?
って感じている人がいるはずなんです。
手工芸というのは
目に見えて仕上がっていきます。
上手にできれば達成感が得られます。
逆に言えば
「うまくできない」というフィードバックも明確に入りやすいので
不安や混乱、不満や不全感を抱きやすい場面でもあるのです。
「Activityはやることに意義がある」
わけではないということを強調したいと思います。
「Activityを通して、自分は自分である」ことを
再体験・再確認できることに意義があるのです。
そのためには
適切にActivityを選択することが必要です。
その方に「向いている」Activityを提供する必要があります。
単に「できることをする」のでは逆効果になることすらあります。
Doではなくて Beを重視するのです。
ぜひ、こちらもご参照ください。












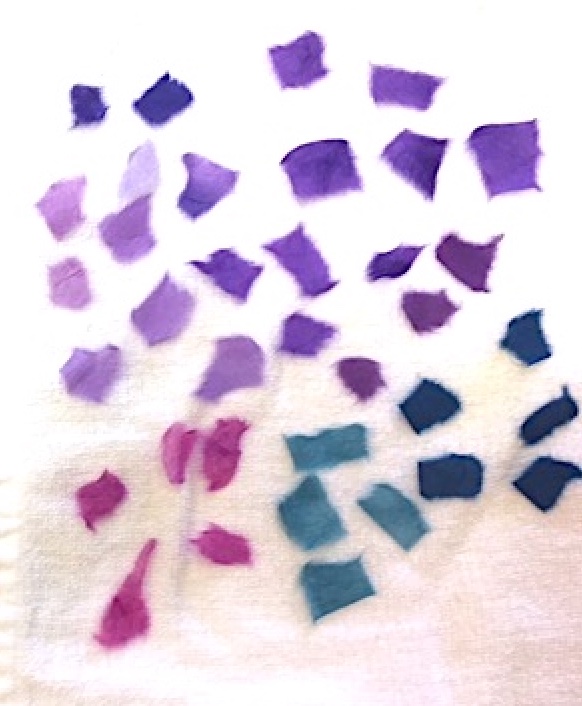







最近のコメント