
ラジオ体操第一は、おすすめのActivityです。
今のお年寄りは
ご自身あるいはお子様のために
夏休みは、早朝に地域の公民館に集まって
首から下げたカードにハンコを押してもらったり押してあげたりしていた世代です。
ラジオ体操第一は手続き記憶として残っていることがとても多いです。
反面、みんなの体操は最近の体操なので手続き記憶としては定着していない体操です。
その違いを踏まえて
二つとも集団体操として組み込むと
手続き記憶や構成障害のスクリーニング、運動習慣などの情報を得ることができます。
また、集団体操中に逸脱言動のある方は
どうしてもスタッフの善意で集団の輪の外へ連れ出されてしまいがちですが
かなりの割合で部分的に運動ということが認識できていることが多いです。
部分的な故に混乱してしまい、その混乱を適切に表現できないだけという。。。
そんな時には、むしろ逸脱言動のある方は
見本を見せている私の真横に来ていただいて
みんなが体操をしているところを視覚的に認識しやすい状況を作ると
逸脱言動は結果としてなくなる場合がとても多いです。
また構成障害のある方には
私の真正面に座っていただくと認識・再現しやすくなります。
物理的距離・空間の位置は認識に影響を及ぼす
「声かけの工夫>声かけ再考>視覚情報>物理的距離」で記載したとおりです。
座席配置の工夫の必要性について配慮がないと
その方の本当の能力発揮を阻害してしまうことがあるのです。
また、誘導にも工夫が必要です。
「体操しましょう」と誘っても拒否される方の中に
輪の中に入るのは嫌だけど、遠くから参加しているという方も少なくありません。
あるいは、誘導に拒否したけれど
いざBGMが流れ体操が始まるとご自身の席で体操していることもよく見かけます。
言葉だけに頼らずに行動をよく観察する
ということは、強調してもしすぎることはないと感じています。
「何を」するか
ということはかなり検討されても
「どのように」行うか
ということについては、まだまだ検討の余地があると考えています。









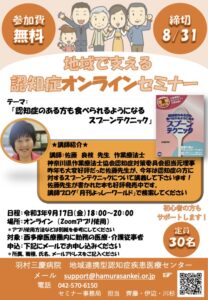


最近のコメント