
声かけの工夫>聴覚情報>声 のところでも書きましたが
私はいつも認知症のある方が使っている声の大きさやトーンに合わせて
自分の発する声を同調させるようにしています。
大きな張りのある声で話す方には
私も張りのある大きめの声で
ゆっくり穏やかな声で話す方には
私もゆっくりと穏やかな声で
それと同じように
認知症のある方がよく使う表現に合わせた声かけをするようにしています。
冗談で返してくる方には
私も冗談を多用し
丁寧に接する方には
私も礼節表現を多用します。
例えば
場所の移動の促しって
結構、抵抗される場合が多いかと思います。
使う言葉の質的側面( 援助の言葉・意思表明の言葉 と 目的の言葉・手段の言葉 )
を踏まえて移動を促す声かけをするだけでなく
認知症のある方の特性、よく使う表現にそって声かけします。
冗談を好む方には冗談を交えて
丁寧な方には礼節表現を強調して
そうすると
移動の促しをしても
あんまり拒否されることってないんです。
拒否されるとしたら
その方が拒否する何らかの必然があります。
そこを探らないと。。。
つまり
認知症のある方への対応の工夫は
生活障害やBPSDで困った時にだけ行うものではなく
関わる時には常に認知症のある方の能力と困難(障害)と特性を踏まえて
対応しています。
いつも
評価をもとにした関わりをしています。
常に意識的・意図的に。
その方それぞれに。
記憶の連続性、近時記憶障害の程度については
HDS-RやMMSEをとらなくても
ふだんから意図的に関わっていれば
かなりの程度で把握することが可能です。
(HDS-RやMMSEをとることを否定しているわけではありません)
そして最も重要なことは
把握した情報は関わりに活用することです。
私たちが暮らす上では
普段無自覚に参照している経過や状況・背景といった前提要件があるわけですが
近時記憶障害があると、それらの前提要件を忘れてしまいます。
認知症のある方に対して関わる時に
それらの前提要件について触れてから「今必要な話」をするのか
触れなくてもすぐに「今必要な話」をして良いのか判断して会話しています。
おそらくですが
多くの人がこういった、やろうとすれば誰でも今すぐにできる工夫
といったことをしていないんじゃないかと感じています。
〇〇法とか〇〇理論とか、何か効果的な特別なものがあると思っている。。。
認知症のある〇〇さんが
受け取りやすく、受け入れやすい、言葉や対応を選択して使う。
それは
〇〇さん固有のもの。
△△さんには、△△さんが受け取りやすく、受け入れやすい、別の対応をする。
そのためには
〇〇さんの状態、△△さんの状態を的確に把握しなければ。
対応の工夫は、オーダーメイド かつ 何の問題も起こっていない時から日常的に



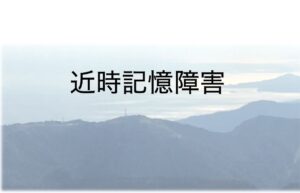




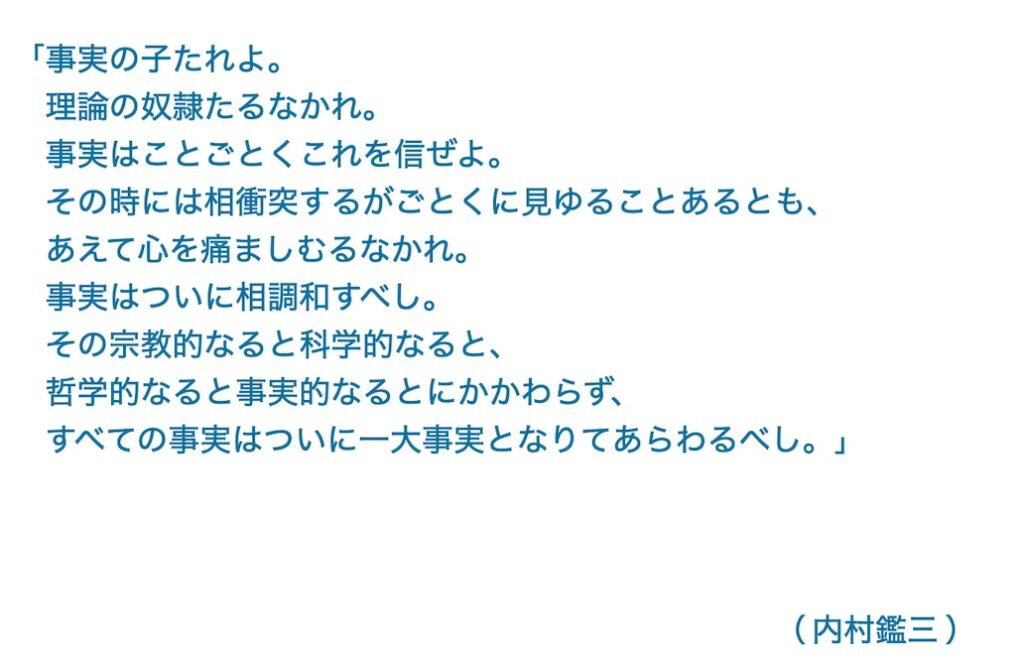






最近のコメント