
看護介護職は変則交代勤務
看護介護職は、変則交代勤務であり
まさにチーム、集団で働く職種である
OTは常に1体1の関係性の中で対象者を見ています。
グループを扱う時にも、基本は対象者個人から出発してグループを手段として用います。
ところが
看護介護職は
担当病棟、担当ウイングという集団の中に自身も置いているし
担当病棟、担当ウイングという集団の中で対象者も見ている
作業療法士が対象者の方に対して
Activityを提供する時には
実際のリハ場面以外のところで
Act.の準備をしたり仕上げをしたり片付けをしています。
それと同じように
看護介護職も実際に対象者に対して
処置や与薬などの医療行為や
食事・排泄・更衣などなどの日常のケアを
実際に提供する場面以外のところで
準備や片付けなどもしています。
しかも、それらをチームで遂行するわけで
その日その日に割り当てられた役割通りに遂行することが
絶対要件・大前提となっています。
他者が役割通りに遂行していることに対して信頼もしています。
疑問を抱いていたら仕事が成り立たないという職種でもあります。
その信頼に応えるためにも役割をきちんと遂行しようという意識が働きます。
変則交代勤務だけでなく
昨日と今日が同じ日勤であっても
担当ウイングが異なる、違う対象者集団を担当することも起こり得ます。
夜勤帯になれば担当する対象者の数が大幅に増えることになります。
異なる職員が異なる集団を対象にミスなく仕事をすることが求められる
内服や点滴など一歩間違えたらとんでもないことも起こり得るので
そんなことにならないように
明確化されたことをきちんとすることが第一義的に求められる
職種だとも言えます。
リハスタッフは
対象者の行動変容を促す職種ですから
変化に即応していくという意識を根底に持っています。
変化があって当たり前
変化がなくては困ります。
この変化に即応するという面は
実は、看護介護職にとっては難しい側面でもあります。
(決して否定しているわけではありません。念の為)
リハスタッフと看護介護職の間での
連絡や伝達の行き違いというのはよく起こりますが (^^;
職種としての根本的な成り立ちが違うので
優先順位も異なってくる。
むしろ、起こって当たり前と思っていた方が良いと考えています。
現実的な働き方が違えば、自ずと観え方も違って当たり前です。
良い悪いの問題ではなくて
違うという当たり前のことを踏まえて
じゃあ、どうしたら少しでも対象者のために、チームに貢献できるのか
ということを具体的に考えていきます。
連携を良くしよう!
などと抽象的総論的に考えるのではなくて
今、目の前で起こっている連絡・伝達の困難という
具体的に解決・改善すべき事象を少しでも良くするために
自分の立場でできることは何か
とあくまでも困りごとという現れ方をしている行動を変えることを考えます。
さらに言えば
リハスタッフと看護介護職との連絡がスムーズにいかないという場合は
実は看護介護職の中でも連絡がスムーズにいかないということもあるあるです。
つまり、看護介護職内部の課題がリハスタッフとの間で表面化しているだけという。。。
対象者のために、チームに貢献できる努力はしますが
看護介護職内部の連絡伝達の不備という課題には介入すべきではないと考えています。
看護介護職の管理者が現状をどう認識しているのかということと
課題解決の優先順位をどう考えているのかに
大きく関与することだからです。
連絡伝達がスムーズな組織というのは
個々の職員が情報の取り扱いにきちんと留意していたり
優秀な管理職が必要に応じて介入したり何らかの仕組みを導入していたり
といったことがあるんじゃないかと思います。
そうでない場合には (^^;
チームに貢献するという意識を持って
どうしたら連絡伝達が少しでもスムーズになるだろうか
ということを個々のケースに沿って具体的に行動について考えていきます。
それは次の記事で。
1 飲みニュケーションでは連携の問題を改善できない
2 プロのチームスポーツに学ぶ
3 連携という抽象論ではなく具体的に改善していく
4 情報伝達において前提要件を認識する
5 看護介護職は変則交代勤務
6 情報伝達の工夫:使う場所に情報提供
7 対象者が変われば職員も変わる
8 そもそも何のための連携?
9 たったひとりでも変わる意義













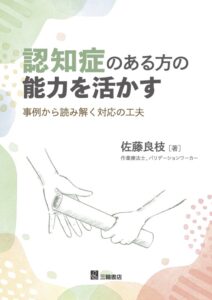 2026年4月刊行予定
2026年4月刊行予定
最近のコメント