
食事をため込んでしまう方
喉頭が不完全挙上している方の場合に
舌がまるで板のようにガチガチに硬くなっている
ということがよくあります。
そのような場合には
1)食塊認知を促す
2)頭部を支える
3)前舌もしくは下唇をスプーンで押す
ことを続けるだけで、舌が柔らかくなってきます。
1)食塊認知を促す
スプーンで食塊をすくった後にすぐに口の中に入れてしまう人は多いですが
それはダメダメなスプーン操作です。
開口するタイミングを把握しにくいのと
目で見る機会を設けないことで身体の準備をする機会を奪ってしまっています。
目で食塊を見ることで視線を下方に向けることができます。
視線が下がれば体幹は前傾しやすく頚部も前屈しやすいように筋肉が働きます。
逆に
食塊認知を促さないで介助してしまうと
自然な反射として、いきなり食塊が口の中に入ってくるので
体幹は後傾し、頚部の筋緊張も高まってしまいます。
必ず、すくった食塊を口の前でいったん停止させ目で見る時間を作ります。
「ちゃんと食事介助したいけど時間がなくてできない」
という人も多いですが、
この1秒をかけるとかけないでは雲泥の差となって現れてきます。
口腔内にためこまれて10秒待つよりも1秒待つ方が良くないですか?
たかが1秒、されど1秒
この1秒に大きな意味があります。
2)頭部を支える
身体はつながっているので
舌が硬いという場合にはたいてい頚部の筋肉も硬くなっています。
筋肉の余分な緊張をほぐすために
頭部を支えながら食事介助をします。
ティルト型車椅子やリクライニングではなく
普通型車椅子に座っている方でも支えます。
頚部後屈している方はもちろん、
頭部が前に突出しているような方にも必要です。
後頭部に手や腕を当てて、頭の重さを支えます。
ポイントは「支える」ことで、見た目を修正することではありません。
重さを支えられたことによって
筋緊張は緩和しますから、頚部の筋肉がほぐれます。
そうすると舌の筋肉もほぐれてきます。
3)前舌もしくは下唇をスプーンで押す
上記の1)と2)によって、舌が動きやすくなる状況を作りました。
舌が動きやすくなれる環境が整ったところで
舌の動きの再学習を促すのです。
スプーンの背で前舌をしっかり押します。
押された舌は、作用ー反作用の法則によって
上に上がる動きをするようになります。
人によっては、舌を触られることを嫌がったり
舌そのものに触れられない場合もありますから
そのような時には、下唇をスプーンの背でしっかり押すようにします。
舌がガチガチに硬い場合でも
多くの場合にムセることもなく
最初はためこみもみられないものです。
だから、食べ方を観察していない介助者は
努力して食べていることに気がつきにくい。
舌は本来しなやかに動く者です。
だから食塊再形成もできるし送り込みもできる。
それがガチガチになっていたらものすごく大変です。
でも、対象者はすごく頑張って努力して送り込みをしています。
過剰な努力に力尽きた時にためこみが起こります。
ためこみは結果です。
スムーズに舌が動かせない結果。
本当はためこんでいるのではなくて、送り込みが難しいのです。
送り込みができない結果として、ためこんでいるのです。
問題は、そのような状況に陥るまで
対処できなかった介助者の側にあります。
「ため込んで飲み込んでくれない人にどうしたら良いか」
という質問をよく受けますが、本末転倒です。
もっと早く気がつけば、もっと早く対処ができて
食べる方も介助者も、もっとラクに食事場面を共有することができたのに。。。
でも、まだ希望はあります。
今の能力でラクに食べられて栄養が取れる食形態に変更します。
問題は舌の動き・口腔期にあるので、
ごく薄い粘性の液体の栄養補助食品が望ましい。
舌に負担をかけずに、舌の動きの再学習を図ります。
ため込んでいるから、誤嚥しないようにトロミをガッツリつけるのは
効果がないどころか、逆効果、やってはいけないことなんです。
再学習が進めば
食形態を段階的に上げることができます。
1)と2)と3)は同時に行うことが大切です。
たくさんの方が舌が動くようになってきた経験をしています。
そして、意思疎通困難と呼ばれていた方が
舌の柔らかさを取り戻した時に、意思疎通が可能になってきます。
「自分の世界に閉じこもっている方」
「何を言っても怒りっぽい方」
「反応がない方」
と言われていた方に
「どうもありがとう。気をつけて帰るんだよ。」と言われたり
会話が成り立ったり
ということは、山ほどあります。
こんなにわかっていたんだ。。。
どんなに辛かっただろう。。。
基本的なスプーン操作を徹底していれば防げることです。
一番は予防です。
予防できなかったとしても、
できるだけ早期に誰か一人でも気がついて
的確な対処ができれば悪化は防ぐことができます。
よく、飲み込む力の低下という言われ方をしますが
実際には、筋力低下が問題ではないことの方が多いです。
協調低下、協応の混乱ということの方が圧倒的に多いのです。
お年寄りの歩行能力の低下が筋力低下という問題設定がなされていますが
筋力低下は結果として起こる
その前提として身体協調の低下が先に起こっている
ということと全く同じコトが違うカタチで現れているのです。








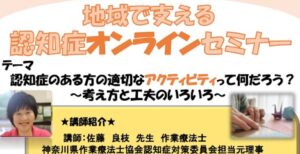




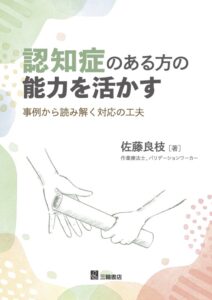 2026年4月刊行予定
2026年4月刊行予定
最近のコメント