
もう30数年前の学生の頃の実習の想い出とその後日談です。
当時、OTの養成校はまだ少なく、首都圏でもK学院とF学院、S学院、そして我々の母校のH学院を合わせて4つしかなかったと思う。大学はまだなくて、いずれも専門学校だった。
私はこの中で最も新しいH学院に3期生として入学した頃の話である。当時ようやく3学年そろったばかり、当然1期生には先輩はおらず臨床実習はまだこれから、2期生はまだ評価実習にも出ていない、我々3期生は入学したばかりでもちろんまだ何も知らなかった。
殆どの学生が寮で生活していたのだが、そこに毎週ではないが土曜日になると時々F学院からAさんという学生がやってきた。
彼は大学も出ており(中退かも?)歳も少し上で、社交性があり話も面白く親切だった。1期生の先輩と研修会か何かで知り合って親しくなったようである。
前述のように新設校の我々は情報に乏しかったので、彼がもたらす情報は貴重なものがあった。彼の訪問は先輩たちに大いに歓迎され、当然のこと酒宴が設けられ我々1年生も呼ばれ、彼は寮に泊まり翌日帰るのであった。
Aさんもその辺りの事情を察し、義侠心というのか、新設校であるH学院のヤツらは不安だろうと、仲間意識や友情から好意的に遊びに来てくれたものと思う。いずれは同業者になる仲間でもある。まだOTは全国でも数百人しかいない。
寮は2人部屋で狭いのだがギューギューに詰めると15人位は入ったであろうか、二段ベッドなので二階席も3~4名分あった。
私は酒は好きではないが、当時そうやってよく飲んだことは楽しい想い出だ。
H学院出身者は酒飲みが多い、酒に強いといった噂もあるようだが実際にはそうでもなく、噂の出処はそうやってよく飲んだことを話題にするからではないだろうか?
寮で飲めば金もかからないし、時間も気にせず屡々酔いつぶれていた。
そのF学院からの使者Aさんの話でこういうのがあった。
当時実習先は学生どうしの話し合いで決めており、K学院もF学院も同様であり、我々のH学院もそれを踏襲していた。今は学生の希望を基に教官が決めているのかな?
おそらく今と比べると実習はかなり厳しく、というか厳しい所とそうでもない所の格差が大きかったと思う。
ここで厳しいというのは臨床のレベルが高いということではなく、必ずしも学生に対する要求水準が高いということでもない。
端的に言えば、イジメや嫌がらせに近いことも少なからずあったのである。今では考えられないが酒をガンガン飲まされるところもあった。
Aさん曰く、
K学院の実習先で「悪のH病院※」という所があり、この病院に実習に行くと散々甚振られた挙句に必ず不合格となり、今までに合格した学生は誰もいないと言う。
※「AのH病院」という全く別の病院もあり、それをもじった名称で、病院自体が悪いわけではない。念のため。
当然又聞きだが、K学院で実習先を決めたときの話。
クラス委員が「H病院に行きたい人はいませんか?」と問うたところで、もちろん手を上げる人など誰もいない。
ところが静まりかえり皆が戦々恐々とする中、「誰も行かないなら、私が行きます」と手を上げた勇者がいたという。
当然のことながら皆からウォーっ!と歓声が上がり、拍手鳴り止まず…。
しかし、果たしてやはりその学生は落とされて留年したという。
その話を聞いて、我々1年生は大いに感銘し、他のクラスメイトにもそれを伝え、「実習先を決めるときは自分の利益ばかり考えずにお互い配慮しあって決めよう。自己中はよくない。」と言い合い、後に後輩にもそれを伝えた。
そのおかげかどうか、実習先を決めるときも特に揉めることも無く、さほど不平不満も恨みっこもなく、割とスムーズに決めることができたと思う。
今となっては、なるべく良い実習先を、と確保してくれた教官の苦労も偲ばれる。
私個人に関しては、もちろん落とされたくはないし、厳しい所はイヤだけどよくわからないし特に希望もなく、皆よりも歳も上だし、皆が決めてから残った所でイイやということにしていた。
実際には後で教官が調節することがあり、私も1回か2回、呼び出されて、ココは厳しいのでごむてつ君は無理だと思う、○○さんと交代してもらってこっちの病院に行った方が良い、○○さんも既に快く了解してくれている、などと言われて変更になったことがあった。
当時の学生、特に我々のクラスメイトの女性は、積極的で向上心の強い頑張り屋が多く、厳しくても勉強になる所を志望する傾向があった。まったく当時も今も頭が下がる。ホント、御世辞じゃなくて。
そのおかげで、私も実習では行く度か危機もあったし、すんなりと上手くいったわけではもちろんないが(自分の未熟さと勉強不足が悪いんだけど)、何とか落第はしなくてすんだし、結局、我々の3期OTは病気で欠席した1人を除いて、留年する学生もなく、国試にも全員合格し卒業することができた。
これには後日談がある。
K学院の「玉砕の勇者」が誰であるのか?気にはなっていたのだが、10年以上も経ってようやく判明した。
私が後に入職した大学で同僚になったY先生である。
私:「へぇーっ、あの時の話はY先生のことだったのかぁ~。H学院では『K学院の玉砕の勇者』として、語り継がれていたんですよ」
「ところで、何であんな所を志願したんですか?」
Y先生:「いや~、実は知らなかったんだよね。寮生ではなく通学してたので情報が入らなくて」
私:「そうなんですかぁ(笑)」
「でも、先生の尊い犠牲は、H学院では教訓として生かされ、決して無駄にはならなかったですよ。」
Y先生:「ふ~ん、そうなんだ…(ちょっと悲しげに)」
私:「でもハッキリ言って、あんな実習先とSVでは勉強にもならなかったでしょ?」
Y先生:「いや、そんなことはない。勉強にはなった。少なくとも私にとっては。後悔はしていない。」
私:「えぇっー?そうなんですかぁ?いったい何が勉強になったんですか?」
「少なくとも臨床の勉強にはならなかったでしょ?」
Y先生:「そう言われると困るなぁ。でも、勉強にはならなくても修行にはなった」
「自分の欠点・弱点を認識せざるを得なくなったし、自分を変えていこうと思うきっかけにはなった」
「学院の教官にも随分お世話になったし感謝している」
私:「でも割に合わないよなぁ。そんな所に行かなくても修行はできるし」
正直言って、辛い目にあっただけで修業にもなっていない気がするけど…
その実習先のSVは後に大学教官になり、自分で(取り巻きかも知れないけど)Wikipediaには「ノーベル賞に一番近い作業療法士」なんて書いていた。実際にどこまでやったのか知らないけど、「動物実験をやって作業療法の研究をする」なんてことも言ってたはずだ。
しかし、彼ももう10年以上前に大学を退官になり、程なくして亡くなったようだ。もはや有名でもないしほぼ忘れ去られた人である。知ってる人は思い出したくもないだろうし。
実習に行って落とされたY先生も何年か前に大学を辞めている。
あの頃はまだまだOTは知られておらず我々もわからず、何もかも手探りだったものの志と熱意だけはあり、夢も希望もあった。
あれから40年近く経ったが、皆、夢を実現したのだろうか?
私に関してはOTは辞めて、別のところで実現したけど。いや、まだその途上である。
「あの頃」 ワイルド・ワンズ(湘南サウンドの代表的なバンド)
時々海にも行ったな。ランニングするのに丁度よい距離だった。
夕陽と共に ワイルド・ワンズ
いずれも作曲は加瀬邦彦(ex.ブルージーンズ→ワイルド・ワンズ)
彼は歌謡曲の作曲家として有名だが、世界的にも珍しい12弦ギタリストで黄色いYAMAHAを半世紀以上弾き続け、今は息子さんが引き継いでいる。
とは言えギターのコレクターでもあり、いろいろな人に貸し出され多くのレコーディングで使われている。
ついでにこれも。今はおやじバンドの定番曲。
R.I.P. 寺内タケシとブルー・ジーンズ Terry & Blue Jeans/ 雨の想い出 I’ll Remember In The Rain (1965年) – YouTube
これもね。当時の雰囲気がよく伝わる。
R.I.P. 寺内タケシとブルー・ジーンズ Blue Jeans/ユア・ベイビー YOUR BABY (1965年) – YouTube



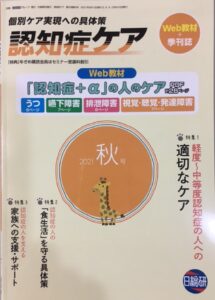








最近のコメント