
アーシュラ・K・ル=グウィンの
「西のはての年代記 II ヴォイス」p.177に
「わたしたちの求めるのは真の答えではない。
我々の探す迷子の羊は真の問いだ。
羊の体のあとにしっぽがついてくるように
真の問いには答えがついてくる。」
という言葉があります。
この本はファンタジーですが
リアルな世界で現実に起こっていることを
仮想の物語として教えてくれます。
難解な神のお告げを人々に伝える、優れた「読み手」の言葉として記されたのが冒頭の言葉です。
この言葉に触れた時に、衝撃を感じました。
あまりに端的に明確に言い当てられたように感じたからです。
私は常々、評価・状態把握・アセスメントの重要性を説いています。
_「車椅子で前傾してしまう方への対応」_ にも記載してありますので
もしよかったらご参照ください。
私は過去に
様々な主催者から様々なテーマで多数の講演依頼を受けてきました。
講演後の質疑応答で良くあるのが
「〇〇という状態の方がいるんですけど、どうしたら良いのでしょうか?」という質問です。
講演内で「表面的に問題を捉えるのではなく、どんな障害と能力が反映されているのかを捉える」
ことの必要性を事例をあげて強調したにもかかわらずです。
それだけ、「〇〇という時には△△する」というハウツーを当てはめる思考過程(思考ですらないと思いますが)が現場では蔓延しているのだと思います。
「対応の引き出しを増やす」という言い方で
多くのハウツーを知ることが奨励されたりしています。。。
そして、あてはめたハウツーが適切かどうかもわからないので
効果があったかどうかも確認することすらできないでいるのです。。。
どうしたら良いのか分からずに困っているのではなくて
実は、その方に何が起こっているのかわからなくて困っているのだから
何が起こっているのかをわからなくてはなりません。
そして、何が起こっているのかがわかっていないという自分自身にきちんと向き合い
どうしたら、何が起こっているのかをわかることができるようになるのだろう?
と自分自身に問いかけなければなりません。
ところが、多くの人はこれらの過程をすっ飛ばして
「どうしたら良いのか?」と他者に尋ねるのです。
あるいは、カンファレンスとして皆で相談・検討しあうのです。
どうしたら良いのかは
何が起こっているかがわかれば
自然と一本道のように浮かび上がってくるものです。
あとは浮かび上がってきたものを具現化すれば良いだけです。
(その技術にも熟練が必要ではありますが)
ここをすっ飛ばしてしまえば
誰に聞いても
どんなにたくさんの人と相談したり考えたりしても
「結果が出ない」「有効な方策とならない」
のは当たり前の話です。
何が起こっているのかは
その時その場にいるその人にしかわからないのに。
関与する人の在り方が変われば、認知症のある方の能力をどこまで引き出せるかも変わります。
(そんなことは自分自身を振り返れば当たり前にしていることではありませんか?)
認知症のある方自身の中でも、障害と能力は変動します。
その場にいない人にわかるわけがないのに
一番わかるはずの自分自身に問いかけるのではなく
他の人に尋ねるのです。
答えは
その時その場にあるのに
どこか他にあると思っているのです。
たぶん
養成過程や卒後の就職先や研修でも
そのような臨床姿勢しか知ることがなかったのだと思います。
かく言う私だって、教えてもらえたことはありませんでした。
そして、長い試行錯誤の果てに、ようやく臨床姿勢こそ重要なのだとわかるようになったのです。
でも、
今まで問い方を間違えていたのなら修正すれば良いだけです。
ズレた問いだから、ちゃんとした答えが返ってこずに結果も出なかった。
だとしたら、真に問うことができるようになれば
ちゃんとした答えが返ってくるし結果も出せるようになります。
自分自身の臨床姿勢、在り方こそが問われているのです。
一度、問い直す道を選ぶことができたなら
2度とハウツーの当てはめなどできなくなります。
それがどれだけ不毛なものか、よくわかるからです。
そして、問い直しの道は生涯続きます。
わかったと思ったことでも
時を経て、状況を変えて、同じことは何度も形を変えて繰り返し起こります。
そのたびごとに何回もわかり直します。
より深くより実感を持ってわかり直すことができるようになります。
科学は過去の知識の修正の上に成り立つ学問です。
今、本当に問われているのは、基本的な臨床姿勢なのです。

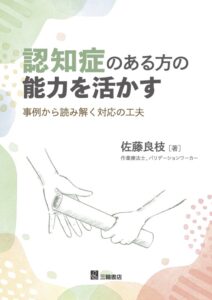 2026年4月刊行予定
2026年4月刊行予定
最近のコメント