
頸部後屈したまま、食事介助するのは危険です。
ここまでは、よく知られています。
ところが、じゃあどうしたら良いのか?ここは、あまり知られていません。
たいていの人は、後頭部にクッションを当てたり、頸部を中間位方向に動かします。
その結果、どうなったかというと、クッションを当てても頸部は後屈したままだし
他動的に頸部を中間位方向に動かしても「作用ー反作用の法則」でかえって後屈がひどくなってしまいます。
実は、下の図1のように、頭部を支えれば良いのです。

<図1>
支える場所は、通称「盆の窪」と呼ばれる場所です。
頭頂部に手を当ててそのまま後方へずっと手をさすりおろしていくとひっこんでいる場所があります。そこを支えるととても安定します。
試しに少し上や少し下に手を当ててみてください。
違和感を感じると思いますが、盆の窪では違和感を感じることはないと思います。
そこに手を当てるだけです。
この時点ではまだ頸部を前に向かって、前屈方向に(見た目としては中間位に)動かしてはいけません。
手を当ててしばらくすると頭の重さを軽く感じる瞬間があります。
軽く感じるということはつまり、頸部中間位方向への動きをご本人が行なえたということを意味します。
拘縮はあってもガチガチに固まっているわけではないのです。
頭の重さを支えつつ動かすことは大変でも重さを支えてもらえたので動かせるようになるのです。

<図2>
そこで、ご本人が動かせる範囲まで頭の重さを支えながら頸部中間位まで動かすと、またガチっと動かないことを感じます。
そうしたらそこで頭を支えたまま待つのです。
するとしばらくするとまた頭の重さを軽く感じるようになるので再び可能なところまで動かします。
このエピソードは実はとても重要な意味を持っています。
「修正するのではなく助けるという視点に立つことがポイント」なのです。
どの職種も見た目の表面だけを見て、
あるべき理想から差し引きマイナスで現状を捉えて
理想に近づけるように修正しようとします。
私が提案しているのは、
現状という見た目から埋もれている能力を見出すということです。
埋もれている能力を発揮しやすいように助けるということです。
修正するか助けるか、外からは同じように見えるかもしれませんが、
関与者の意図は真逆であり、この意図こそが対象者に伝わるのです。
話を元に戻します。
対象者の頭部の重さを支えながら食事介助をするのは大変なことです。
そんな時には支えている側の手で対象者の肩に触れることで腕の負担を軽くすることができます。(図3)

<図3>
そして忘れてはいけないことは、
座位で頸部後屈してしまうような方は臥床時の姿勢にも問題を抱えているということです。
たいていの人はどの職種であれ、
臥床時のポジショニングと座位時のポジショニングの関連性と
その意味を観察・洞察できていません。
本論のようなケースでは頸部後屈が改善できてよかったで終わりにしてしまいがちです。
そうではなくて、頸部後屈を引き起こすような身体の状態がある。
座位では頸部後屈という見た目で現れるが、
臥位ではどのように現れているのかを把握し対処すべきなのです。
*図1〜3は「認知症のある方でも食べられるようになるスプーンテクニック」(日総研出版)より
と同時に
臥位でのポジショニングも見直します。

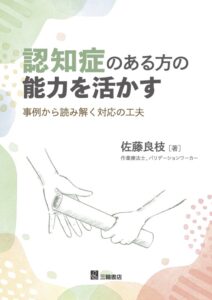 2026年4月刊行予定
2026年4月刊行予定
最近のコメント