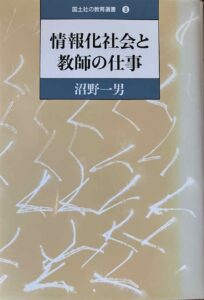
臨床大会での講演をきっかけに
教育工学の沼野一男先生の著書を久しぶりに読み直しました。
初版の刊行が1986年ですから40年近く前の本ですが
内容は全く古びていません。
ティーチングマシンが導入されて
個々の子どもの習熟度に合わせたプログラミングが為されるとなると
人間である教師ができること、すべきことは何か?
という問いが為されます。
まさに、教育とは何か?教師の仕事とは何か?
ということを否が応でも突きつけられるのです。
ティーチングマシン導入以前は
教授目標の妥当性については内容に関する議論・検討が主だったが
導入以降は目標の明確性が議論・検討されるようになってきたとのこと。
リハの世界では、目標の、内容の妥当性について提唱・議論されていますが
教育界では既に数十年も前に経験済みの事象だったんだ。
まさしく、私が目標設定において従来から提唱しているカタチの重要性について、
教育界でのお墨付きをもらったような気持ちになりました。
目標の内容の妥当性を提唱・議論する人たちは
「目標とは何ぞや」という概念が理解できていない現状について
認識できていない人たちが多いと感じています。
目標とは何であって何でないのか、
明確に言語化できる人の本当に少ないことを認識できるためには
目標の概念理解ができることが必須という、皮肉な現実があります。
目標の内容の妥当性の吟味検討ができるためには
最低限、目標を目的や方針や治療内容ではなくて
目標を目標というカタチで設定できて初めて
内容の妥当性を検討できる土俵に乗ることが可能となります。
大多数のセラピストは、目標を目標というカタチで設定できていないのに
内容の妥当性の吟味検討提案をするという、意味のないことをしているのです。
この本の真髄は
後半の「問う」授業の展開にあります。
まさに、ソクラテスの意図を見事に具現化していたのでしょう。
著者の凄みを感じました。
「問う」授業を展開するためには
教師にも学生にも準備とエネルギーを要求されます。
考えてみれば、本質的なことを実践するために
事前の準備が必要なのは言うまでもないことです。
最先端の論文を読んだり
海外の理論を学び実践することも悪いことではありませんが
本質に触れる経験がないと上滑りするんですよねぇ。。。
私たちセラピストも
長年の蓄積がある教育界から学ぶことって多々あると思います。
表面的なことに流されるのではなくて
本質に触れる・向き合う機会が必要なんだということを深く感じました。

さてさて
遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。
今年が皆様にとって
ますます善い年でありますように。。。
既存の常識とは相容れないような提案がなされた時に
否定され提唱者が迫害を受けるのは枚挙にいとまがありません。
古くはガリレオ、ゼンメルワイス、小笠原登。。。
同時に後世になって彼らの正当性が認められたこともまた歴史が証明しています。
勇気を持ってファーストペンギンの立場に立った彼らは素晴らしいと思いますが
同時に彼らの周囲で実践をし続け、継承し続けた名もなき人たちがいたからこそ
彼らの正当性が後世になって認められたのだとも思っています。
「科学は嘘をつかない。科学は多数決ではない」
「科学は過去の修正の上に成り立つ学問」
この言葉を胸に
今年も実践を続け、志ある人たちの勇気を支えられるようなサイトを目指していきます。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。


最近のコメント