
認知症のある方の中には
「変化に弱い」「こだわりが強い」
という理由で、こちらの提案を受け入れていただけないケースもあると思います。
転倒・転落予防策を実行したいと思っても
「でも変化に弱いから」
「こだわりがあるから環境を変えることを了承してもらえない」
という意見が出て結局有効な手立てが打てないこともあるのではないでしょうか。
でも、本当に?
「変化に弱い」「こだわりが強い」方も確かにいるでしょう。
ただし、そう言われている方の中に
何を提案されたのか、理解できなくて「嫌」「そんなことしなくていい」と
言っている方も確実に含まれていることはお伝えしたいと思います。
たいていの人は
言葉だけで提案しようとします。
提案する職員は、イメージを持って言葉で伝えているのですが
認知症があると、その言葉が意味しているイメージを抱けない
ということもよくあります。
再生と再認を説明する時によく事例として紹介していますが
「あなたの好きな岡晴夫の歌を聴くために、リハビリ室に行きましょう」
と声をかけると「嫌よ、私、そんなところに行かないわ」と拒否されますが
リハビリ室までご案内すると「あぁ、ここね、ここなら昨日来たわ」と言って
ノリノリで岡晴夫の歌を視聴され口ずさんだりします。
この場合は、聴覚情報(リハビリ室という言葉)では
実際のリハビリ室をイメージすることができないけれど
リハビリ室のドアを開けて実際の場所を見るという視覚情報によって
昨日来たことがある、という体験を思い出せるということを意味しています。
「嫌よ」と言って拒否したけれど
岡晴夫の歌を聞くのが嫌だったのではなく
よくわからない場所に連れて行かれるのが嫌だったということなのです。
ところが、職員は、リハビリ室という言葉から実際のリハビリ室をイメージすることが
当然のようにできるので、認知症のある方がイメージできないということを推測できにくく
配慮ができない、あるいは、「岡晴夫が好きって言ってたけど私が聞いたら嫌がったわよ」
と事実誤認をしてしまったりするのです。
また、今使っているスプーン以外に変更することをすごく嫌がる
と言われている場合もありますが
「そのスプーンだと使いにくそうだから、スプーンを変えても良い?」
と言われても、どんなスプーンになるのか想像もできなければ
躊躇したり拒否しても当然だと思います。
ましてや、今までにスプーンのために食べたくてもうまく食べられない経験をしてきたとしたら
余計にそうなると思います。
ポイントは
理解しやすいように、声かけの内容を「見える化」する
ところにあります。
先のスプーンの場合だと
実際に変更したいスプーンの実物を見ていただく
その時に
「お試しで1回だけ使ってみて」
「使いにくかったら今まで通りの元のスプーンに戻すから」
という言葉も添えるようにしています。
ただ、この場合も気をつけないといけないケースもあって
神経症的な傾向のある認知症の方の場合に
明らかに食べこぼしが減って操作も楽になっているのに
「使いにくい」と言明する人もいたりします。
そういう時には、「食べこぼしが〇〇くらいだったのが、△△になった」という
事実を明確に伝えるか
変更の前後でビデオを撮って見比べてもらったりしてから説明したりします。
どんなに優しく親切に丁寧に説明しても
説明手段が言葉である限り、認知症のある方は実は理解できていないこともある。
「言葉」を下支えしている「イメージ」の共有ができていないことを
職員が気がつかないこともあるのです。
(が、職員は自身が良かれと思ってやっていることなので方法論に問題があると認識しにくい)
理解できない結果として「拒否⇨変化に弱い」「拒否⇨こだわりがある」という表れになり
その結果としての表れだけにとらわれて、現実的な改善案を提案できずにいる。。。
本当の困難は
「聴覚情報で提示されても理解しにくい」ということなのに
そこだけを切り取って「理解力低下」とされがちですが、そうではなくて
「視覚情報(文字、実物)で提示されれば理解できる」のです。
そういう方は本当に多いものです。
そして、そのことを自覚できていない職員も本当に多いものです。。。
さらには
こちらの提案を全て却下していたわけではなくて
提案した対応が不適切だったから却下していた、(これは当然のことです)
その提案の不適切さを自覚できないというケースも少なくなくて
適切な提案であれば、ちゃんと受け入れてくださる
新たな環境や突発的な予定でも対応できるのだ
ということも多々あります。。。
つまり
「変化に弱い」「こだわりが強い」
と言われている方たちのすべてが対応困難というわけではない
「変化に弱い」「こだわりが強い」という結果に反映されている本当の困難を見出し
今よりも良い結果を生み出せるような適切な提案をできること
この2点は実は私たちの側の問題なのだと自覚することが大切です。
今までは、このような視点を持つことができなかったから認識できなかった
でも、認識することができれば問題を的確に把握することができるようになり
改善していく可能性が高い
それは、認知症のある方にとっても、私たち職員の側にとっても
伸びしろであり、希望でもあるのだと考えています。


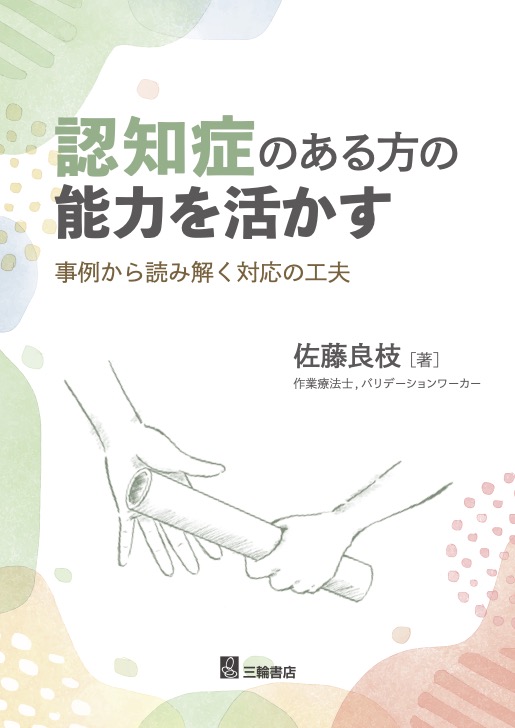



.jpg)


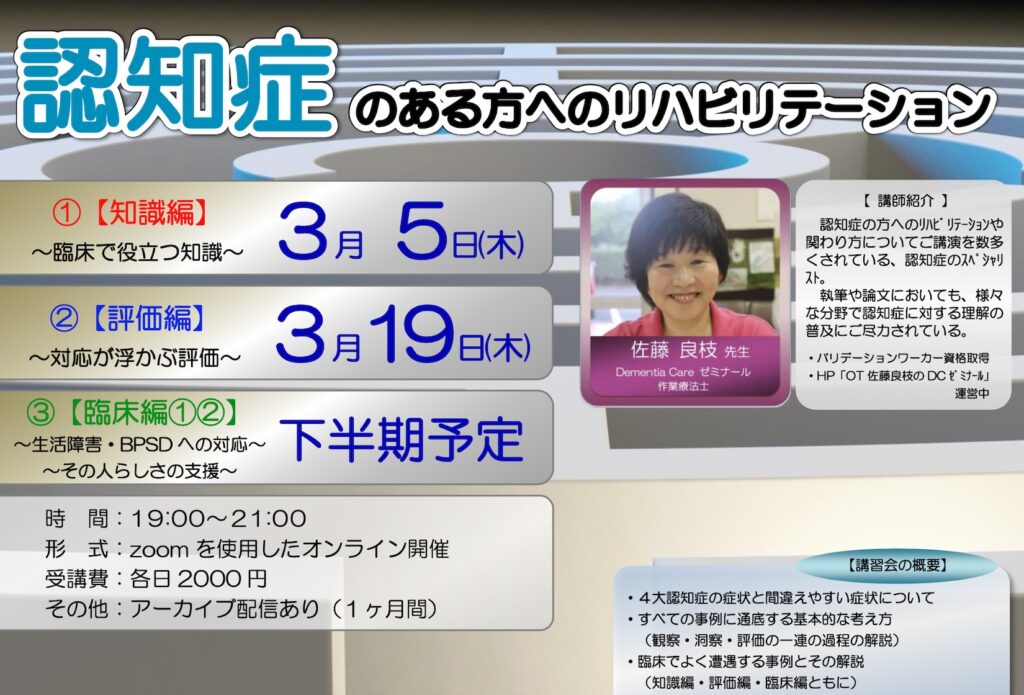



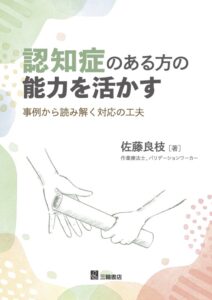 2026年4月刊行予定
2026年4月刊行予定
最近のコメント