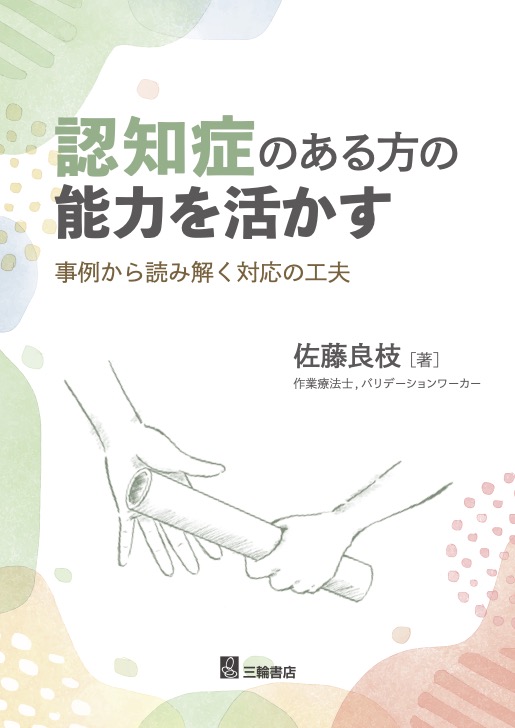
ここ数年、なんだかんだと苦闘していた、
認知症のある方への対応の工夫についての本
「認知症のある方の能力を活かす 事例から読み解く対応の工夫」が
4月中旬〜下旬頃に_三輪書店_さんから刊行される予定となりました!
かつて、本当に困っていた若き日の自分が
あったらいいなと思う内容をまとめてあります。
メインの読者としては
私は作業療法士として仕事をしていますので
やはり、作業療法士の人には読んでほしいなと思いますが
作業療法士でなくても、理学療法士や言語聴覚士の人
ケアマネージャーや介護職の人や看護師や相談業務に従事している人
もちろんご家族の方にもきっとお役に立てるんじゃないかなと思います。
国は「新しい認知症観を」と普及啓発事業を進めています。
確かに、認知症だから何もできないわけじゃないし
認知症になってもできることはたくさんあるけれど
私はさらにもう一歩推し進めて
たとえできなくなったり困ったりしたとしても
その中にも「できる」要素があるのだと
困りごとの中にこそ改善・解決のヒントがあるのだと
だからこそ、対応の工夫・声掛けなどの人的環境も含めた環境調整の意義があるのだと伝えたい。
個々の実践の集積はあったとしても
理念の具現化とは違う側面で為されていることもあったり
理念と個々の実践を結びつける考え方は示されていないことが多いのが実情ではないでしょうか。
事実に向き合い、事実から学ぶ
わからないこと、できないことを受け入れつつも諦めないで向き合い続ける
当たり前の臨床姿勢こそ、常に在り続けることは難しいものですが
その大切さを日々実感しています。
この本の表紙の画像を見せていただいた時に
「これこそ私が願っていた本だ!」と感じました。
私がよく引き合いに出す言葉に
スティーブ・ジョブズの
「人は形にして見せてもらうまで何がほしいのかわからないものだ」
という言葉がありますが、まさしくその言葉を体験した瞬間でした。
暖かくて優しい雰囲気で
多様性を感じさせつつ、
混沌とした現実の中に能力があり、能力が合理的に発揮されるイメージ
バトンの受け渡しのイラストからも私の必死さが滲み出ているようで大好きです。
私の作業療法士としての集大成がこの本であり
認知症のある方とご家族の困難が少しでも少なくなるように
そのために対人援助職の人たちに本当に必要な内容が詰まっていると思います。
これから先の未来に若い人たちの手によってその内容を再構築してもらえるようにと願っています。
本という形になって結実したのは
私の意図を表紙に具現化してくださったデザイナーの方や
的確な文章表現のためにご尽力くださった校正担当の方
そして何よりもいつも丁寧に明確に橋渡しをしてくださった編集室のMさんとTさんのおかげです。
心から感謝申し上げます。
若き日の自分は本当に何もわかっていませんでした。
今だって学ぶべきことは多々あるし
わかっていないことやできないことがどれだけあるのだろうか見当もつきません。
そんな中でも明確にできた部分もあると思います。
それは、今まで私が出会ってきたたくさんの認知症のある方のおかげです。
深く感謝申し上げます。
発売開始まで、今しばらくお待ちください。




.jpg)


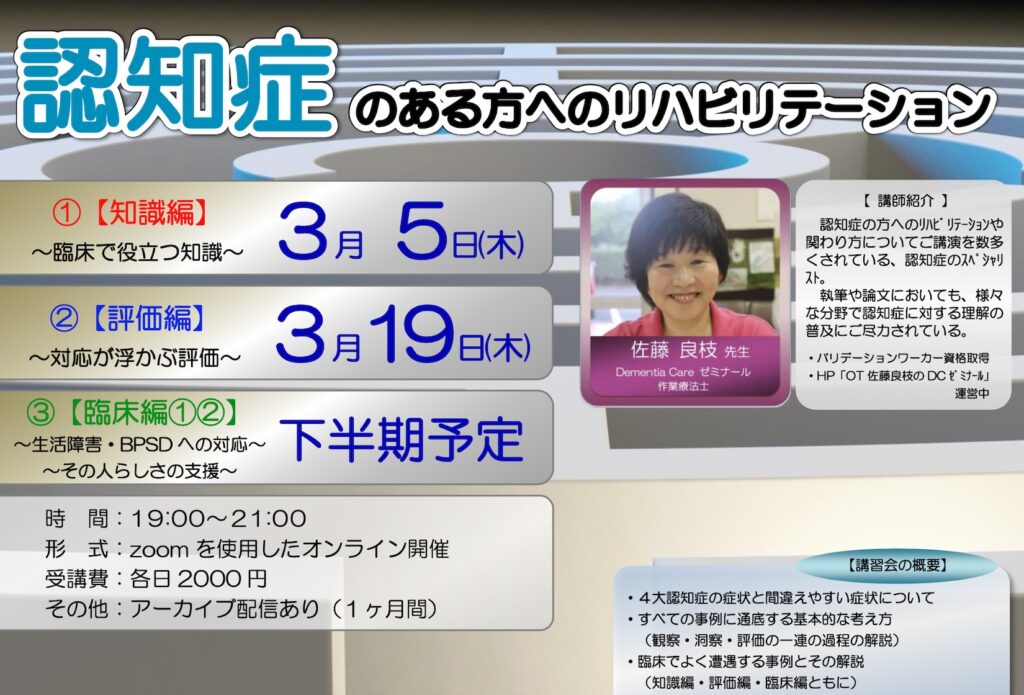




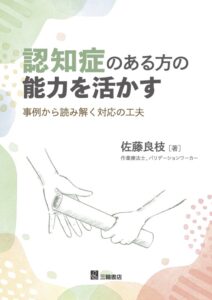 2026年4月刊行予定
2026年4月刊行予定
最近のコメント