
かつて
評価に際し
「あぁも考えられるし、こうも考えられる」と言ったOTが結構いましたが
その言葉に反映されている臨床姿勢は、評価とは真逆のものです。
「これは違う、あれも違う」と確実に除外できるものは除外していくことから始めるべきです。
また
知識のない人に限って
「いろいろなことを考えなくちゃいけない」と言ったりしますが
「下手な考え休むに似たり」
知識がない人が考えて逆効果になることは山ほどあります。
また、対象者のことを勝手にこちらが考えて良いものではありません。
こちらが考えるのではなく
相手に教えてもらうことが大切です。
ただし、
相手、認知症のある方は、今自身に起こっていることを説明してくれることはありませんし
どうしたら楽になるか、食べやすくなるか、座りやすくなるか、歩きやすくなるかを
言ってくれることもありません。
でも、
言葉にしてくれなかったとしても
身体は雄弁に物語っています。
身体の動き、行動というもう一つの言葉で明確に伝えてくれています。
私たちがすべきことは
身体の動き、行動という、もう一つの言葉にきちんと耳を傾けることです。
耳を傾けることができるようになるためには知識が必要です。
知識の多寡によって現実の見え方はまったく異なってきます。
杜撰な対応をしている人は
大雑把にしか現実を見ていないから
その人にしてみたら、その人が見えるレベルにおいてはちゃんと対応しているわけです。
表面的に杜撰な行動を修正するように指導しても有効ではありません。
対象者の困惑や能力を見落とし能力低下している部分しか見えていないから、杜撰な対応ができるのです。
見落としている部分があることを現実的に具体的に示すことで
見落としの自覚を促すような指導が必要です。
(最初はものすごい抵抗を示されることを覚悟していた方が良いです。
的確な指導ほど強い抵抗が返ってきます。
まぁ、これは指導者の職務ですから、そのような役割でなければそんなことは回避して
上には上がいるのだと、自身の能力向上に時間とエネルギーを注いだほうが絶対良いです。)
知識があるから目の前で起こっていることを見落とさずに観察できる
行動というもう一つの言葉に耳を傾けることができ
何が起こっているのかを洞察することができる
そして、一本道のように浮かび上がってくる「どうしたら良いのか」をつかむことができる
あとは、つかんだ「どうしたら良いのか」を具現化する技術がありさえすれば
ピンポイントで対象者の困りごとを解消し、
埋もれていた能力をより合理的に発揮する援助が可能となります。
就職した場所がどんな場所であっても
学ぶことは可能です。
たったひとり、自分だけでも、可能です。
周りは関係ありません。
選択するのは、自分です。
自分が知らない、わからない、できないことと
対象者の能力が限定していることを混同しているセラピストは少なくありません。
そんな風になりたくないと願っている人は
OJT、その時々でわからないことに出会った時に調べることから始めましょう。
そして今すぐにでも、目標を目標というカタチで設定することから始めましょう。
え?と思うかもしれませんが
目標設定の能力は臨床姿勢と密接に関連しています。
対象者の目標を目標というカタチで設定できるからこそ
方法論を現実的に検討することができるようになります。
ケースごとに概念を明確化していく過程を吟味することになるので
表面的な作業としては目標設定をしているのですが
同時にメタ認識として概念の明確化のトレーニングを蓄積していくことになるのです。
目標を目標というカタチで設定できさえすれば
必ずや的確な目標、目標の内容の質の担保が可能となります。
目標を方針や目的や治療内容と混同していれば
いつまで経っても的確な目標、目標としての質の担保には決して辿り着けないのです。
そして、臨床場面でも事実を事実として観察することができないままなのです。
はっきり言って
目標を目標として設定できていない人で優秀な人に会った試しがありません。
いくら地位があったとしても、いくら名前が知れ渡っている人でも臨床能力に秀でていない人は山ほどいます。
自身の目標設定に疑問を抱いたり自信のなさを自覚できていない人の実践はいい加減なものです。
逆に
地位も名声もない人でも、本当に優秀な人だってちゃんといるのです。
優秀な人は、仮に目標を目標として設定できていなかったとしても
目標設定の難しさを自覚しているものです。
目標設定なんてカンタン!って言ってる人に限って
「目標とは何ぞや?」と尋ねられる時に答えられないものです。
目標は内容ではなく、まずは形、記述の仕方が重要なのです。
このことは、教育工学の第一人者の沼野一男氏が
「情報化社会と教師の仕事」という本のp.55で
「何を目標にしなければならないかということではなく、教授目標の記述の仕方を問題にする。」
と記載しています。
この本は1986年が初版ですから、
既に40年以上前に教育分野で言われていること、達成してきたことに
リハやケアの世界では、まだまだ全然追いつけていないことを示しています。
目標設定の問題については、重要なことなので
また別の記事で書いていきますが
目標とは何か、良い目標を設定できるようになるための練習方法など
このサイトで既に記載していることもありますので
興味のある方は _こちら_をご参照ください。
ちょっと話がズレてしまいましたが
セラピストの能力はいろいろなことが関連しています。
だから、なんでもいいから、何か一つ、とことん向き合うことができさえすれば
それは、自身の成長に向けてのブレークスルーの道を開くことになります。
ところが、忙しい臨床を抱えて、とことん向き合うというのは
なかなかできるものではありません。
下手をすると、あまりの辛さに無自覚のうちに安易なハウツーものに流されてしまうこともあるでしょう。
安易なハウツーに流されず、臨床上に直接的にも間接的にも有益なものが目標設定だと考えています。
目標設定でメタ認識をトレーニングすることで
臨床観察の眼を自分一人でも涵養することが叶うのだと感じています。
行動というもう一つの言葉を
ありのままに聴けるように
科学的な観察ができるように
観察が非科学的なのではなく
非科学的な観察しかできないことが問題なのです。

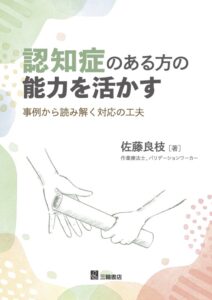 2026年4月刊行予定
2026年4月刊行予定
最近のコメント