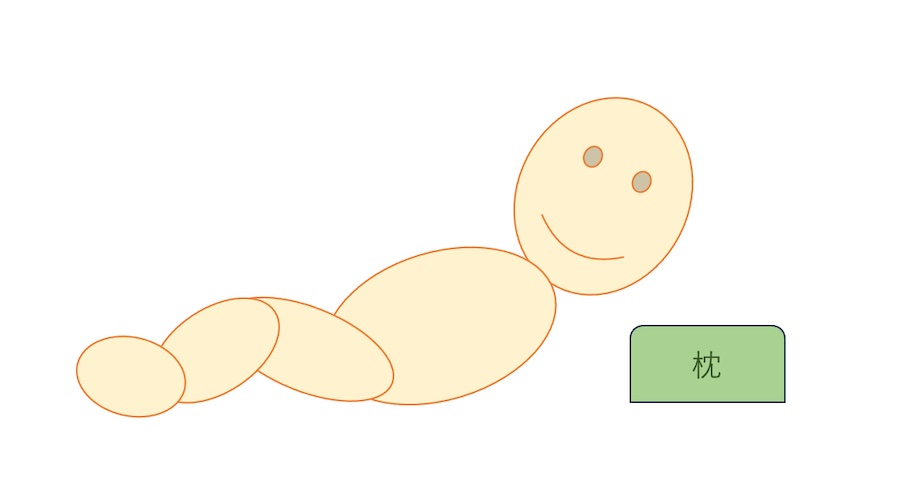
高齢者施設での
現場あるあるのよくある誤解と適切な対応策についてご説明します。
臥床介助をすると
頭が持ち上がっていて枕につけることができない、頸部前屈してしまう
というケースによく遭遇します。
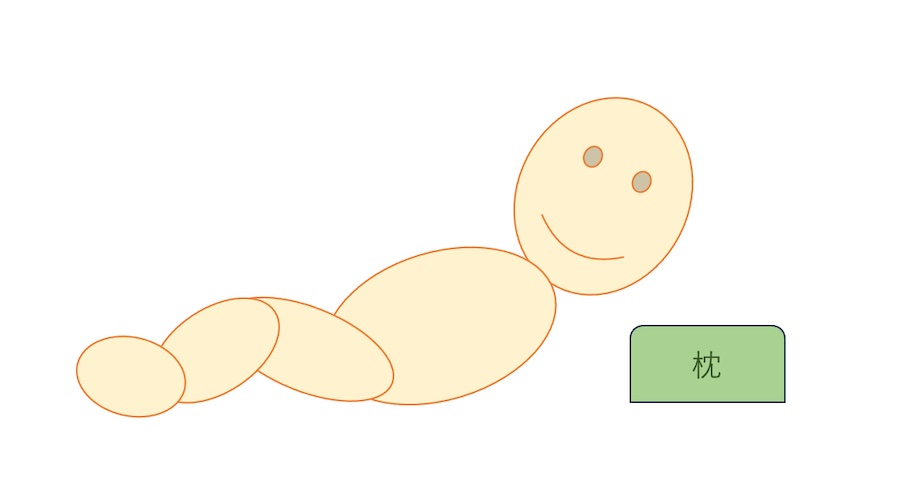
このような時にどのような対応がなされるかというと
そのひとつが
こんな風に頭を下に押すようにして
「頭を枕につけてくださいね」という方法です。
ところが、実際には頭を枕につけてくれるどころか
もっと頭を持ち上げられてしまって諦めた。。。という場面に遭遇したことのある人は多いはずです。
なぜなら表面的に頭を枕につけてもらおうとして頭を押すと
「作用ー反作用の法則」によって逆向きの力、頭を持ち上げようとする力が働くからです。

そこで、諦めた人が次にするのが、
下の図のように枕を高くしたり、枕の上にクッションを重ねたりして
持ち上がっている頭部に合わせた対応をしてしまうことです。

ここで、ちょっと思考実験をしていただきたいと思います。
もしよかったら、実際に体験していただくことをオススメします。
仰向けに寝ます。
頭を空中にもちあげるように、頭部挙上します。
そのままの姿勢を保ってみてください。
いかがですか?
腹筋がプルプルしてきませんか?
全身に余分な力が入ってしまっています。
そして、この状態が慢性的に続くと全身がより一層固くなってしまいます。
このような状態を放置されると
離床しても、「臥位で頭部挙上」と同じ状態つまり頸部前屈してしまいます。
そうすると食事介助も大変になってしまうんですよね。。。
じゃあ、どうしたら良いのか?
下の図のように
挙上している頭部に、介助者が枕を持って押し当てるようにします。

そして、枕を頭部に押し当てて少しだけ上に持ち上げるようにしてから
「頭を下げます」と声をかけ
ごく弱い力で少しだけ頭を下に向かって押しながら枕を持った手も下げていきます。
ここで、もしも頭を持ち上げてしまうようなら
下げるのはいったん止めて
「大丈夫ですよ」と言いながら枕をしっかりと頭部に押し当てます。
3秒くらいそのまま待ってから、もう一度
いったん頭部に押し当てた枕を手にしたままで少しだけ上に持ち上げた後で
軽く頭を下に向かって押してから枕を持った手も下げていくと
頭を枕につけて臥床することが可能となります。

つまり、一見、頸部前屈という拘縮を示しているように見えても
実は可動域制限ではなくて、筋緊張の問題、勝手に力が入ってしまっている問題
というケースの方が圧倒的に多いのです。
(もちろん、中には本当に頸部前屈位に拘縮してしまっているケースもあります。
そんな時には、頭部とベッドの隙間を埋めるように枕を重ねる対応が適切となります。)
問題は臥床介助時に頭が持ち上がってしまうということは、常時、頸部前屈方向に力が入ってしまっているということです。
頸部前屈するように力が入り続けているから臥床させても同じ状態になってしまうのです。
そこで、そんなに力を入れなくても大丈夫なのだと伝える、どうしたら力を抜くことができるのかを伝えることが求められているのです。
ところが、見た目の頸部前屈を拘縮と誤認して
単に頭部と枕のスペースを埋めるようにクッションを当てているだけでは、
筋緊張を緩和させることができないどころか、
離床時に頸部前屈するように力を入れて座っているという不自然なあり方を増悪させてしまうことになりかねません。
そもそも、なぜ離床時にそんなに力を入れて座らざるを得ないのか、そこをきちんと評価・アセスメント・状態把握することが必要です。
よくあるのは、安楽に座れていないから頸部前屈するしかないので、
安楽に座れるように座位のポジショニングを見直すべきです。
まず股関節に着目します。
股関節の90度屈曲位を取ることが難しく臀部が前ズレしてしまうので、
滑り落ちないようにバランスを取ろうとして頸部前屈させているということが多々あります。
このようなケースでは
ティルト型車椅子を用いて、背部でも体重を支えられるようにすることで
臀部への負担を減らし、股関節を屈曲しやすい状態を作ることが可能となります。
また、クッションの前方の下に
タオルを巻いたものを滑り止めネットでくるんでから設置すると
前座高を少し上げることができますから前ズレしにくい状態を作ることができます。
この時のクッションは、少し柔らかめの素材を選ぶと
沈み込みが生じて股関節の屈曲を促しやすくなります。
私が推奨するのは_ジェルトロン_で、いろいろな商品があります。
デモ機器として2週間ほどのお試し使用も可能ですし
在宅生活している方向けに、福祉用具としてレンタルも可能な商品もありますので
ぜひ一度ご検討いただきたいと思います。
褥瘡予防効果も高く、尿便失禁しても丸洗いできるのでとても使い勝手が良い商品です。
前ズレしなくなれば、
頭部の余分な前屈をしなくて済むようになり、
結果として臥床介助時に頭部挙上することが見られなくなるのです。
同時に臥床時のポジショニングももう一度見直します。
頭部挙上せずに寝られるようになったのですから、その状態で全身のアライメントを確認します。
ポイントは2つ
1つは
骨盤が傾いていないかどうか
2つ目は
股関節の屈曲を引き出せるかどうか
です。
仰臥位で股関節屈曲位が難しい場合は、側臥位を設定します。
そのほうが下肢の筋緊張が緩和しやすいからです。
設定後には下肢を他動的に動かして
筋緊張が緩和していることを確認します。
もし、力が抜けずに下肢を動かしづらいのであれば、
設定のどこかに無理がある証拠ですから、もう一度設定し直しましょう。


最近のコメント